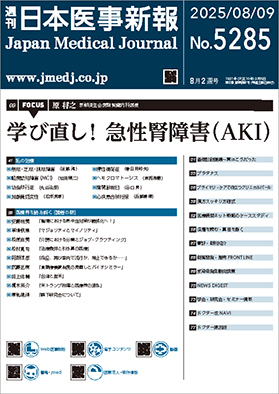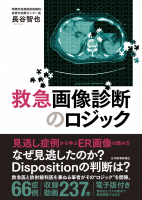お知らせ
特集:CT画像でみる薬剤起因性の腹部救急疾患

田中絵里子
1998年滋賀医科大学卒業。放射線診断専門医。昭和大学藤が丘病院兼任講師,昭和大学横浜市北部病院兼任講師。再現性のある画像診断をめざしつつ,臨床での多様性に学ぶ日々を送っている。
1 抗菌薬
▶抗菌薬に関連する大腸炎として,偽膜性腸炎,抗菌薬関連出血性大腸炎がある。病歴に加えて炎症を示す浮腫の分布が手がかりになる。
▶偽胆石はセフトリアキソン投与に伴い出現する胆泥や胆石様の構造として認められる。

2 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
▶非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は,上部消化管では潰瘍やびらんを形成し出血や穿孔の原因となる。
▶小腸障害では,CT enterographyを用いると膜様狭窄が描出されうる。
3 腸間膜静脈硬化症
▶腸間膜静脈硬化症は,右側結腸の腸管壁から腸間膜静脈の石灰化をきたす。CTや腹部単純X線画像では,特徴的な静脈の石灰化が認められる。加味逍遙散などに含まれる山梔子が関与している可能性が高い。
4 抗凝固療法中の血腫
▶抗凝固療法中には,出血性合併症がある一定の頻度で出現する。どこでも出血する可能性があり,必ずしも1箇所とは限らない。
▶症状は非特異的で,診断に際してはCTやMRIなどの画像診断が有用である。抗凝固療法中の血腫は必ずしも高吸収とならないことに留意が必要である。抗凝固療法に伴う消化管の壁内血腫は,血性腹水を伴う腸管壁肥厚として認められる。
5 カリウム吸着剤投与に伴う消化管穿孔
▶高カリウム血症の治療に用いられるカリウム吸着剤では,硬便を形成し,宿便性穿孔を起こすことが知られている。これらの薬剤は,CTでは高吸収の大腸内容として認められる。
6 腸管気腫
▶薬剤性の腸管気腫には,良性の病態と致死的な病態があり,造影CTによる腸管虚血や壊死の評価が必須であるが,画像所見のみならず総合的に評価する。
7 薬剤による高吸収の胃内容物
▶経口的に摂取される薬剤は,CTにてしばしば高吸収の胃内容物として同定される。多くは病的意義に乏しいが,錠剤の形態を残した薬剤が異物と誤認されたり,溶解した薬剤が出血との鑑別を要したりすることがある。
▶意識障害の診断において,過剰摂取された薬剤を反映した胃内の高吸収域から,急性薬物中毒を示唆できることがある。
8 ヨード造影剤の異所性排泄や遅延造影
▶ヨード造影剤の異所性排泄は,経静脈投与された造影剤の胆道排泄,経口投与されたヨード造影剤の尿路排泄が知られている。
▶造影CT後に,胸水や腹水が遅延造影されて,血性胸水や血性腹水のように見えることがある。