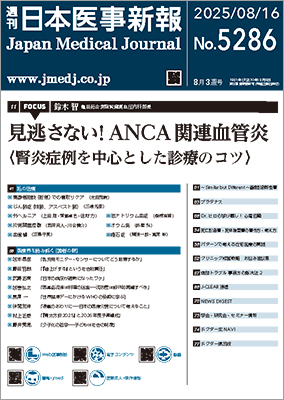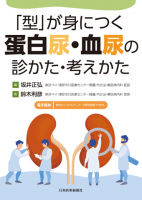お知らせ
急性尿細管壊死[私の治療]

急性尿細管壊死(acute tubular necrosis:ATN)は主に急性腎障害(acute kidney injury:AKI)と診断される患者のうち,特に腎性AKIと判断される場合における代表的な病態である。尿細管上皮細胞が虚血・低酸素,炎症,腎毒性物質などにより障害を受けることで発症するが,必ずしも壊死に至らない程度の病態(acute tubular injury:ATI)も存在しうる。
▶診断のポイント
尿細管上皮細胞の壊死脱落を示す所見は,尿沈渣検査において得ることができる。また,尿生化学検査〔ナトリウム排泄分画(FENa)やバイオマーカー〕により尿細管上皮細胞障害を検出することができる。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
AKIは古典的に腎前性,腎性,腎後性と分類されることが多く,その理由として治療アプローチが異なることが挙げられる。腎前性においては止血,輸液,昇圧および強心などによる腎灌流圧の維持が,腎後性においては閉塞尿路の解除により,比較的速やかに腎機能の回復が得られる。一方,腎性AKIの主たる病態はATNによるネフロン構造の破壊であり,数日~数週にわたり腎機能低下が遷延する。
また,以前は尿細管上皮細胞の再生修復により腎性AKIは完全に回復しうる病態と考えられていた。しかし,最近の疫学研究では,AKIから慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)への移行が,高い確率で生じうることが報告されている。特に既にCKDを合併している場合には,AKI発症率が高いのみならず,その後のCKD進展が加速するため注意が必要である。
ATNあるいはATIに対する特異的な治療薬はいまだ臨床応用には至っておらず,いわゆる保存的治療が腎性AKIに対して行われている。腎灌流圧を維持して可能な限り腎毒性物質を減量・回避すること,肺うっ血などの体液過剰に対しては利尿薬を投与すること,AKIが高度に進展して致死的不整脈をきたしうる高カリウム血症などの酸塩基平衡・電解質異常や利尿薬不応性の体液過剰が生じた場合には,血液透析などの腎代替療法を開始すること,がATNに対する治療方針となる。

残り935文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する