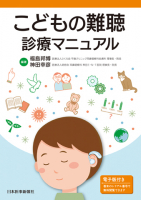お知らせ
喉頭乳頭腫[私の治療]
原因はヒト乳頭腫ウイルス(human papillomavirus:HPV)の喉頭粘膜上皮への感染である。HPV-6型,11型が関与することが多い。発症年齢により,若年発症型と成人発症型に分類することができ,前者は多発し,再発を繰り返す難治症例であることが多い。
▶診断のポイント
以下の①~③を認めれば診断確定に至る。
①喉頭内視鏡で特徴的なカリフラワー様の所見。
②狭帯域光観察(NBI)で,暗青色点状に強調される腫瘍の毛細血管。
③突出した重層扁平上皮と間質の中心に毛細血管を持つ,切除生検の特徴的な病理組織。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
切除またはレーザー蒸散による外科的治療が第一選択となる。一方で手術による制御困難例には様々な補助療法が試みられている。
手術にあたっては2つの留意点がある。1つ目は,腫瘍の性質から複数回の手術が必要となる可能性があること,2つ目は,基本的には良性であるため,可及的に音声の温存を図ることが求められること,である。
具体的には,全身麻酔下に行う喉頭微細手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が基本である。本手術に適したメス,鉗子などの器具を用いた切除と,マイクロデブリッダーによる切除,そしてCO2やKTPといった各種医療用レーザーを用いた蒸散が主な手術治療選択肢となる。各施設の手術設備事情により選択されているが,その優劣に明確な差はない。術後音声をできるだけ温存するには,鉗子による操作や,レーザーによる蒸散などで,声帯粘膜深層の声帯靱帯に対する愛護的操作が不可欠である。
手術以外の補助療法は,複数回手術後の再発難治症例に用いられることがある。かつてのインターフェロンαの局所注入から,最近ではcidofovir(国内未承認)の局所注入,HPVワクチン注射などが選択肢として挙げられるが,まだ研究段階である。

残り276文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する