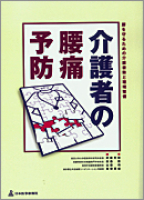お知らせ
「新型多機能サービス」の早期導入を【東大・辻氏が講演】
厚生労働省の元事務次官で、東大高齢社会総合研究機構の辻哲夫特任教授が7月26日に都内で講演し、2025年までに地域包括ケアを実現するために、「新型多機能サービス」を早期に制度化する必要性を訴えた。
「新型多機能サービス」は辻氏が顧問を務める民間組織「地域包括ケア推進研究会」が昨年5月に提言したもの。中重度の居宅要介護者を24時間365日支えるサービスの1つである「小規模多機能型居宅介護」(用語解説)について研究会は、制度が創設された2006年以降、高齢者の1人暮らし、高齢夫婦世帯が増加し、「通い」よりも「訪問」のニーズが増加しているとの認識を提示。変化したニーズに応えるために規制緩和する案を示した。具体的には、「登録定員を50名に引き上げて、訪問サービス利用増に対応」(小規模多機能の定員は29名以下)、「看護職員の配置は必須とせず、訪問看護ステーションを併設」(小規模多機能は1人以上配置)などとしている。

講演で辻氏は、既存の在宅支援サービスについて、地域包括ケアの理念である「最期まで地域で暮らす」ことができるようにシームレスに整備されていないとの問題意識を強調。「有料老人ホームやサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)はお金がないと入れない。中所得層が住み続けてきた家、地域で最期まで生ききることができるためのポイントが新型多機能サービスの導入だ」と訴えた。
![]()
【小規模多機能型居宅介護】:「通い」「泊まり」「訪問」の3つのサービスを合わせて提供し、要介護者が中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するサービス。現在の事業所数は4984カ所。全国的に普及が十分進んでいないため、2018年度介護報酬改定の議論において、普及に向けた人員基準や利用定員等の在り方が論点の1つとなっている。