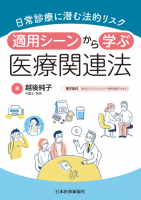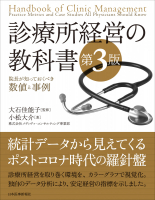お知らせ
■NEWS 介護医療院の約7割が協力医療機関との連携体制を確保―24年度改定検証調査
厚生労働省は3月31日、社会保障審議会・介護給付費分科会の介護報酬改定検証・研究委員会に、2024年度介護報酬改定の効果検証調査の結果を報告した。高齢者施設等と医療機関の連携体制に関する調査からは、介護老人保健施設と介護医療院の約7割が省令の定める要件を満たす協力医療機関を確保できていることが分かった。
24年度改定では介護保険施設などの施設系サービスにおいて、入所者の急変時に、(1)相談、(2)診療、(3)入院の受け入れ(病院が協力医療機関になる場合のみ)―に対応できる協力医療機関を定めることを義務化(3年間の経過措置あり)。特定入所者生活介護などの居住系サービスについても(1)、(2)を満たす協力医療機関を定める努力義務を課した。

調査結果によると、要件を満たす協力医療機関を定めていた割合は、介護老人福祉施設56.6%、介護老人保健施設70.0%、介護医療院72.4%、特定施設入居者生活介護67.3%―などとなった。いずれのサービスでも24年度改定以前から協力医療機関を定めていた施設が8割を超え、協力医療機関数の平均は2医療機関程度だった。
■「協力医療機関連携加算」の算定は会議開催の要件クリアが課題
要件を満たす協力医療機関を定めている施設における「協力医療機関連携加算」の算定率は、特養27.2%、老健54.1%、介護医療院46.4%、特定入居者生活介護62.0%、認知症対応型共同生活介護33.7%―だった。加算を算定していない施設の理由では、施設・居宅系サービスともに「定期的な会議の負担が重く、会議を行えていない」など、算定要件の定期的な会議の開催の充足を困難視する回答が目立った。
入所者の急変時の対応状況では、①老健以外は要件を満たす協力医療機関を定めている施設のほうが、医療機関への相談件数が多い、②老健、特定入居者生活介護以外は要件を満たす協力医療機関を定めている場合のほうが、協力医療機関への受診が多い―ことが明らかになった。また、入院が必要となった際の対応では、いずれのサービスにおいても要件を満たす協力医療機関を定めている場合のほうが、救急車による搬送が少なく、救急車による搬送が行われたケースでは老健を除き、入院先の医療機関と事前調整した上で救急車を呼んだ割合が高い傾向がみられた。