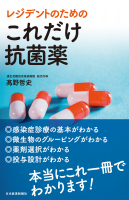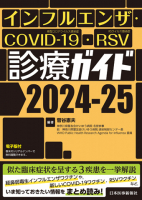お知らせ
変遷するClostridium difficile腸炎
【米国感染症学会(IDSA)ガイドラインupdate 2017】
Clostridium difficile(C. difficile)は,偏性嫌気性のグラム陽性桿菌であり,医療関連感染の原因菌である。医療従事者や病院環境などを介して伝播し,院内発症する腸炎の原因菌として知られており,抗菌薬の使用,高齢者,重篤な基礎疾患などが危険因子である。近年,市中発症のC. difficile腸炎(CDI)が海外で増加傾向との報告があり,わが国においても今後注意が必要である。また,CDIは毒素により引き起こされるが,国内でも,高病原性のbinary toxin産生株が,いまだ数は少ないが報告されている。

CDIは再発頻度が10~30%と高く,これまで軽症例ではメトロニダゾールの投与が推奨されてきた。しかし,2018年に改訂された「米国感染症学会(IDSA)ガイドライン」では,再燃しにくいバンコマイシンが第一選択薬とされた。そのほか,わが国では18年7月にフィダキソマイシンが再発時の治療薬として承認された。また,toxin Bヒトモノクローナル抗体製剤であるベズロトクスマブは,再発抑制に有効であるが,薬価が高額であることから適応を慎重に判断することが求められる。
特に再発を診断する際には,イムノクロマト法によるキットにおいてトキシン陽性となりやすいため,診断の根拠としないよう注意する。
【参考】
▶ McDonald LC, et al:Clin Infect Dis. 2018;66(7): 987-94.
【解説】
樽本憲人*1,前﨑繁文*2 埼玉医科大学感染症科・感染制御科 *1講師 *2教授