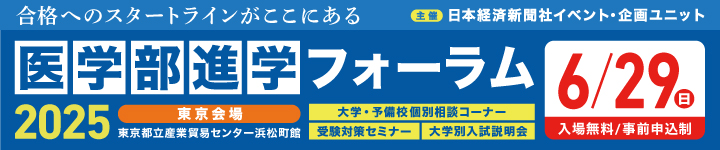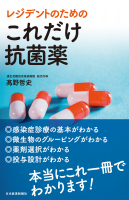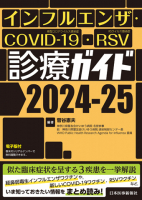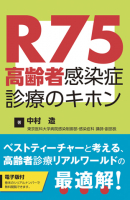お知らせ
鳥インフルエンザ[私の治療]

A型インフルエンザウイルスは鳥類や哺乳類に広く感染しながら,自然界で維持されている。通常は種特異性を認めるが,トリインフルエンザウイルスがヒトの肺炎や結膜炎の原因となることがある。このような動物由来感染症を鳥インフルエンザと総称する。1997年からH5N1亜型,H7N9亜型トリインフルエンザウイルスがアジアを中心に家禽で流行し,肺炎患者の発生が報告されてきた。致死率が高い(30~50%)ことに加えて,稀にヒト-ヒト感染を認めることから,パンデミックインフルエンザ発生のリスク要因として世界的な関心を集めてきた。2020年9月現在,いずれも患者発生はほとんどみられなくなっている。日本国内では2類感染症に指定されており,患者は感染症指定医療機関に移送され,治療を受けることになっている。それ以外の亜型ウイルスによる鳥インフルエンザは4類感染症に指定されている。
▶診断のポイント
肺炎や結膜炎の患者のうち,発症の2週間以内に家禽との接触歴がある場合には本疾患を疑う。また,患者が発生している地域(中国等)に滞在後2週間以内に肺炎を発症した患者では,本疾患も鑑別診断に加える。

病原体診断(呼吸器検体のPCR検査)は行政検査として実施されるため,最寄りの保健所に連絡する。地方衛生研究所におけるスクリーニング検査が陽性の場合,疑似症患者として届け出を行う。確定検査は国立感染症研究所において実施される。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
中国等の流行地においても,市中肺炎に占める鳥インフルエンザの割合は小さいと考えられる。一方,鳥インフルエンザ患者の呼吸器検体におけるウイルス検出感度は必ずしも高くない。このため,年齢や重症度に応じた市中肺炎に対するエンピリックな抗菌薬投与に加えて,家禽との接触歴や特定の地域への渡航歴を認める場合には,抗インフルエンザウイルス薬を併用することが望ましい。
抗インフルエンザウイルス薬の有効性は臨床試験によって証明されてはいないが,観察研究により,早期投与によって致死率を下げることが示唆されている。高用量・長期間投与が優れているとするエビデンスには乏しい。オセルタミビルが鳥インフルエンザ患者に最も使用されてきた薬剤である。重症患者における経鼻胃管からの投与でも血中濃度は適正だったとする報告がある。オセルタミビル耐性トリインフルエンザウイルスの頻度は稀と考えられている。
結膜炎は一般に予後良好であるため対症療法のみでよい。

残り926文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する