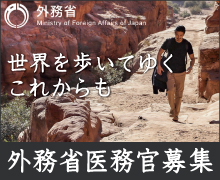お知らせ
心房細動[私の治療]
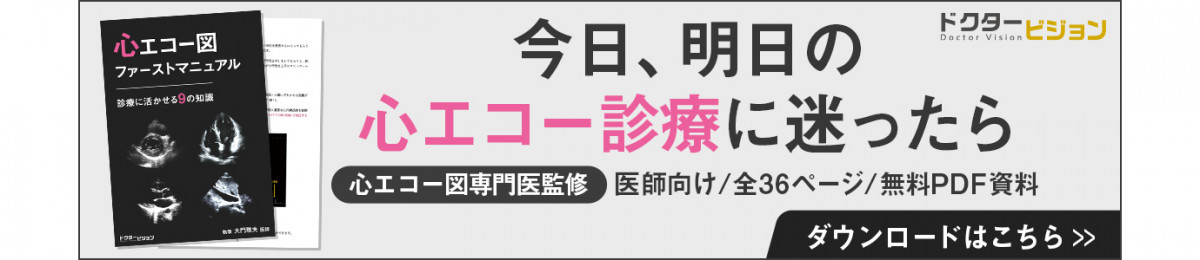
心房細動(atrial fibrillation)の多くでは,左房から肺静脈へと迷入した心房筋からの期外収縮がトリガーとなる。心房細動の持続および慢性化には左房線維化が関与する。心房細動が生じると心房の収縮力が低下するため,左房,特に左心耳に血栓が形成されやすい。これが心原性脳梗塞の原因となる。以前はリウマチ性僧帽弁狭窄症による心房細動が多かったが,近年は高血圧,肥満や糖尿病に合併した心房細動が増加している。
▶診断のポイント
【症状】
発作性心房細動が生じると,動悸,胸部不快感,冷汗,めまい等の症状を自覚することが多い。しかし,発作性心房細動であっても自覚症状のない,もしくは乏しい患者は少なくない。持続性心房細動では,動悸等の自覚症状は経過とともに軽減,消失するが,労作時息切れ等の心不全症状を呈することが多い。

【検査所見】
心房細動は心電図で確定診断できる。12誘導心電図では,P波消失,f波(=細動波),V1,Ⅱ,Ⅲ,aVF誘導で目立つ,QRS出現間隔の絶対不整,といった特徴がみられる。より長時間の心電図記録が可能なホルター心電図や,携帯型心電計(イベントレコーダー)も有用である。心エコー図検査で左房拡大所見を認めることが多い。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
【増悪因子の管理】
高血圧,糖尿病,肥満,睡眠呼吸障害といった因子は心房細動の発生・増悪リスクである。生活習慣の指導や治療で心房細動の軽快・消失が見込める。特に肥満患者においては減量を徹底する。
【脳梗塞リスクの評価】
個々の患者の脳梗塞リスクを評価し,必要に応じて経口抗凝固薬を投与する。
【心拍数の評価】
持続性および永続性心房細動患者が対象となる。安静時心拍数が110/分以上であれば,適切な心拍数調節療法を行う。
【洞調律維持療法の適応判断】
心房細動による症状を評価する。これをもとに,洞調律維持のための抗不整脈薬やカテーテルアブレーションの適応を判断する。

残り1,894文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する