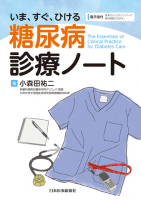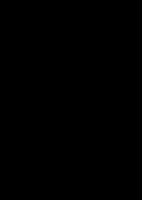お知らせ
【文献 pick up】SGLT2阻害薬で尿酸代謝改善?―RCT 2報併合解析

わが国の「急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)」の68頁に記されているように、「高尿酸血症は、心不全患者にしばしば認められる併存症」である。そして心不全(heart failure:HF)例が痛風を合併すると非合併例に比べ、左室駆出率の高低を問わず、死亡ハザード比(HR)は1.38~1.57の有意高値となる[Ergatoudes C, et al. 2019]。
このHF例における尿酸上昇や痛風発症を、SGLT2阻害薬は抑制できるかもしれない。大規模ランダム化比較試験"DAPA-HF"と"DELIVER"の併合後付解析から明らかになった。JAMA Cardiology誌2月22日掲載の、Jawad H. Butt氏(グラスゴー大学、英国)らによる論文を紹介する。

解析対象になったのは、"DAPA-HF"と"DELIVER"に参加した1万1007例中、試験開始時に「痛風」診断歴が明らかだった1万1005例である。両RCTの対象はいずれも利尿ペプチド濃度上昇を伴うNYHA Ⅱ度以上HF(DAPA-HFは左室駆出率「≦0.4」、DELIVERは「>0.4」)で、SGLT2阻害薬による「HF増悪(入院+救急外来受診)・心血管系(CV)死亡」抑制作用がプラセボと比較された。
平均年齢は約70歳で、10.1%に痛風診断歴(既往)があった。
まず痛風既往の有無がHF転帰に及ぼす影響を見ると、「HF増悪・CV死亡」、「HF入院・CV死亡」リスクとも、痛風既往例では非既往例に比べ有意に高くなっていた。HF危険因子等補正後のHR(95%信頼区間[CI])はそれぞれ、1.15(1.01-1.31)と1.16(1.01-1.32)だった。
ただし「CV死亡」のみの比較では有意差に至っていない(1.15[0.96-1.38])。総死亡も同様だった(1.14[0.98-1.33])。
なおSGLT2阻害薬は痛風既往の有無にかかわらず「HF増悪・CV死亡」リスクを同程度、プラセボに比べ有意に低下させていた。
興味深いのは尿酸に対するSGLT2阻害薬の影響である。
試験開始時に尿酸低下薬を使用していなかった9万5566例中3.9%が、22カ月間(中央値)の間に尿酸低下薬を開始していた。そしてSGLT2阻害薬群ではこの尿酸低下薬新規開始のHRが、プラセボ群に比べ0.43(0.34-0.53)の有意低値となっていた。
同様に痛風発作を予防するコルヒチン開始のHRも、SGLT2阻害薬群で0.54(0.37-0.80)の有意低値だった。
なおSGLT2阻害薬による尿酸低下作用は、左室収縮力低下心不全(HFrEF)を対象としたEMPEROR-Reduced試験からも報告されている[Doehner W, et al. 2022]。
これらよりButt氏らは機序こそ「不明」としながらも、尿酸低下作用をSGLT2阻害薬の「クラスエフェクト」と考えている。そしてアロプリノールと一部のACE阻害薬間の交互作用回避、そしてフロセミドによる尿酸上昇抑制などという観点からも、尿酸を低下させるSGLT2阻害薬の併用はHF例にとって好ましいと考察した。
DAPA-HF、DELIVERの両試験はAstraZenecaからの資金提供を受けて実施された。