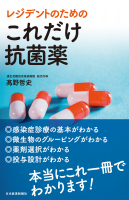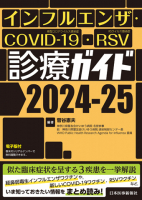お知らせ
インフルエンザ[私の治療]
インフルエンザとは,インフルエンザウイルスAまたはBの感染で引き起こされる呼吸器感染症である。わが国では通常1,2月をピークに11月から4月まで流行する。1〜3日の潜伏期間の後に発症し,上気道・下気道症状に加え,発熱,頭痛,筋肉痛を認める。自然軽快傾向のみられる比較的予後の良いウイルス感染症ではあるが,重症例では呼吸不全や脳症をきたす。
▶診断のポイント
鼻腔・鼻咽頭ぬぐい液を用いたイムノクロマト法による迅速検査が一般的であるが,特異度は高いものの感度は低い(60〜70%程度)点が問題である。特に発症早期(12時間以内)では,感度はさらに低く偽陰性が多くなる。そのため除外診断には用いることができず,検査前確率の高い患者では検査が陰性でも(ないしは施行せず),臨床的にインフルエンザと診断する場合がある。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
インフルエンザは対症療法のみで軽快することもしばしば認められ,発症後数日が経過し既に軽快傾向である低リスク患者では経過観察でよい場合もある。しかしながら,発症早期に重症化するかどうかの判断は困難なことに加え,ノイラミニダーゼ阻害薬による罹患期間短縮,下気道感染や入院の減少,入院患者の致死率低下などが確認されていることから,高リスク患者(高齢者や幼児,妊婦,基礎疾患を有する人など)ではノイラミニダーゼ阻害薬の投与が推奨され,さらに発症早期の低リスク患者でも投与を検討してよいと考える。
薬剤選択に関しては,ノイラミニダーゼ阻害薬の早期投与(発症48時間以内)が基本である。タミフルⓇ(オセルタミビル)が最もエビデンスが豊富であり有効性が確認されているが,投与方法が異なる薬剤や,投与回数が少ない薬剤などが開発され,患者背景に合わせた治療選択が可能となっている。タミフルⓇは内服薬であるが,リレンザⓇ(ザナミビル)やイナビルⓇ(ラニナミビル)は吸入薬であり重症例や気管支喘息合併例を除いて使用でき,ラピアクタⓇ(ペラミビル)は静注薬であり経口摂取が困難な患者でも使用可能である。またイナビルⓇやラピアクタⓇは単回投与が可能であり,治療コンプライアンスの点で優れている。
また,作用機序が異なる(キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害)新しい薬剤として,ゾフルーザⓇ(バロキサビル マルボキシル)が2018年に発売された。低感受性ウイルス株が確認されているものの,成人外来患者ではオセルタミビルと同等の推奨度で投与することが可能である。しかし,重度の免疫抑制状態ではウイルス排出期間の遷延に留意することが必要である。
対症療法としての解熱鎮痛薬はアセトアミノフェンが推奨され,特に小児患者ではライ症候群発症のリスクから,アスピリンや非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の処方は原則禁忌である。症状に応じて鎮咳薬や去痰薬も用いる。
インフルエンザ罹患後に時折,細菌性肺炎を合併し致命的になることがある。一般的な市中肺炎の原因菌である肺炎球菌やインフルエンザ菌などに加え,黄色ブドウ球菌の頻度が高いことが特徴である。抗菌薬治療は喀痰などの各種検体を採取の上,セフトリアキソンやスルバクタム/アンピシリンを初期治療として用いる。

残り845文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する