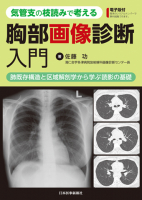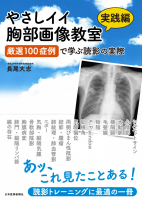お知らせ
じん肺症(珪肺,アスベスト肺)[私の治療]

じん肺とは,粉じんを長期間吸入することによって肺に生じる線維性増殖性変化と定義される。代表的なじん肺として,遊離けい酸の吸入によって発症する珪肺と,アスベスト(石綿)の吸入によって発症するアスベスト肺(石綿肺)が挙げられる。じん肺では,自覚症状より先行して画像所見に出現し,当初は無症状であることが多い。しかし,病状の進行とともに画像所見は増強し,息切れや呼吸困難が出現する。じん肺は,基本的に職業上の曝露によって発症するため,じん肺法によって補償制度が確立している。
じん肺の病態として,体内へ吸引された粉じんは,そのサイズや性質によって異なる部位に沈着し,粉じんごとに特徴的な炎症が惹起される。また発症には,生体側の年齢,免疫状態,基礎疾患の有無なども関係する。いずれの場合も,沈着した粉じんにより気道,肺胞,その周囲の間質に線維化,破壊,気腫化などが生じ,その結果,画像所見の進展や肺機能の低下,自覚症状の悪化が引き起こされる。
珪肺には,緩徐で長期の曝露により生ずる単純型珪肺とその進展型である複合型珪肺に加え,短期間の大量曝露により発症する急性珪肺,急進珪肺が存在する。急性珪肺では肺胞蛋白症に似た病態を示し,急進珪肺では短期間で急激に病状が進行する。
アスベスト肺は,アスベストが細気管支領域に沈着することで発症し,ここから病変が広がっていく。吹付作業など職業的に大量のアスベストを吸入することで発症するが,アスベストが全面禁止となった現在では新規発症はほとんどみられない。
いずれのじん肺においても,粉じんの曝露回避後も,病状が進行する例が多いとされている。
▶診断のポイント
じん肺は労災などの補償の対象となっているため,①一定の粉じん作業歴がある,②厚生労働省によって定められたじん肺標準X線写真の所見と合致する所見がある1),の2点により診断される。

画像所見について,珪肺においては,上肺野優位に存在する辺縁鮮明な小粒状影が特徴的で,一部は融合して大陰影を呈する。アスベスト肺においては,下肺野優位に網状影,すりガラス影などの不整形陰影を呈するが,特に進行例では特発性肺線維症との鑑別は難しい。いずれの場合も,詳細な作業歴の聴取にて,該当する粉じん作業歴の有無を確認の上,診断する。

残り1,268文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する