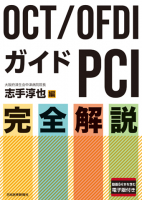お知らせ
【文献 pick up】日本人CV低リスク降圧薬服用例における到達血圧とCV転帰、どれほどの差が?―Hypertens Res誌

降圧薬治療の有用性を考えるには、薬剤あるいは過降圧に伴う有害事象と、降圧がもたらす有効性を勘案する必要がある。そのような観点から貴重なデータが、京都大学の森 雄一郎氏らにより2月14日、Hypertension Research誌で報告された。同氏らが検討したのはわが国における、心血管系(CV)低リスクの降圧薬服用例におけるCV転帰である。到達血圧別にリスクを評価しているため、降圧目標を考えるにあたっても参考になりそうだ。
【対象】
今回の解析対象は、40~74歳で降圧薬を服用していたわが国のCV低リスク92万533例である。診療報酬請求データと毎年の健康診断データから抽出した。「CV低リスク」の定義は、「CV疾患既往なし」または「10年間のアテローム動脈硬化性心血管系疾患リスクが10%未満」(米国ガイドライン評価)である。平均年齢は57.3歳、48.3%を女性が占め、BMI平均値は24.9kg/m2だった。健診時測定の血圧平均値は131.7/81.8mmHgである。

【方法】
脳心血管系疾患(心筋梗塞、脳卒中、心不全、末梢動脈疾患)発生リスクを、観察開始時の健診時測定血圧別に比較した。
【結果】
・脳心血管系疾患発生率
平均2.75年の観察後、2.48%(9.03/1000人年)が脳心血管系疾患を発症した。
・収縮期血圧(SBP)別の脳心血管系疾患発生リスク
まずSBP到達値と転帰の関係だが、「120mmHg未満」まで低下させる有用性は示唆されなかった。すなわち観察開始時に健診測定SBPが「110-119mmHg」だった群でも、比較対象とした「120-129mmHg」群を有意に下回る脳心血管系疾患リスクは認められなかった(諸因子補正後ハザード比[HR]:0.97、95%信頼区間[CI]:0.93-1.02)。さらに「130-139mmHg」群と比較しても、「110-119mmHg」群の脳心血管系疾患リスクに有意差はなかった。
一方、観察開始時の健診測定SBP「130-139mmHg」群では「120-129mmHg」群に比べ、脳心血管系疾患発症の相対リスクは5%の有意高値となっていた(HR:1.05、95%CI:1.01-1.09)。CV低リスク例でもSBPを「<140mmHg」ではなく「<130mmHg」まで降圧する有用性が示唆されるものの、この差を絶対リスクで評価すると「0.09%」だった(2.38% vs. 2.29%:未補正)。また観察開始時の健診測定SBP「140-149mmHg」群でも、「130-139mmHg」群に比べ脳心血管系疾患リスクは有意に高くなっていた(1.05-1.15)。こちらの絶対リスク差は「0.2%」である(2.58 vs. 2.38%:未補正)。
・拡張期血圧(DBP)別の脳心血管系疾患発生リスク
過降圧による虚血性イベントリスク増加が懸念されるDBPだが、観察開始時の健診測定DBP「70-79mmHg」群に比べ脳心血管系疾患リスクの有意な上昇が見られたのは「<60mmHg」群のみだった。
【考察】
森氏らは過降圧に伴う有害事象を中心に考察を進め、CV低リスク高血圧例では高リスク例に比べ過降圧による害の可能性は小さいと結論づけている。
本研究は全国健康保険協会から資金提供を受けた。