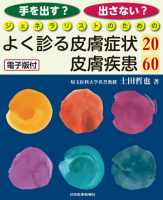お知らせ
特集:クリニックから発信する小児アトピー性皮膚炎治療

2005年昭和大学医学部卒業。昭和大学藤が丘病院小児科入局。2011~13年神奈川県立こども医療センターアレルギー科で専門研修。その後,昭和大学関連病院勤務を経て2018年より現職。日本小児科学会専門医・指導医。日本アレルギー学会専門医(小児科)。

1 アトピー性皮膚炎(AD)と乳児湿疹
- 乳児湿疹は症候群であり病名ではない。
- 乳児湿疹と診断されている児の中に,アトピー性皮膚炎(AD)と診断すべき症例が多いということを認識しておく必要がある。
2 ADとアレルギーマーチ
- かつてADは,食物抗原やダニ抗原の感作の結果として発症する「アレルギーの病気の代表」と考えられていた。
- 現在,ADは,フィラグリン変異などによる皮膚のバリア機能障害に伴う「アレルギーマーチの入口」として位置づけられている。
- 特に乳児期ADは,アレルゲン感作リスクを上昇させ,その後のアレルギー疾患発症に関連する。
3 ADの発症予防
- 保湿剤塗布によるAD発症予防効果は,ハイリスク新生児についてはリスク低減効果を認めるものの,一般乳児についてはまだエビデンスがない。
- 保湿剤の種類や成分,塗布頻度,スキンケアの方法,介入時期などに影響を受ける可能性がある。
- 保湿剤で感作の予防はできず,湿疹があれば,その治療を積極的にする必要がある。
4 ADと神経発達
- ADと子どもの神経発達との関連性については様々な報告がある。
- 小児期ADは睡眠の質を悪化させ,青年期以降のメンタルヘルスと関連性がある。
- 学童期や思春期のADは自己肯定感の低下を引き起こし,うつ傾向や希死念慮の頻度が上がる。
5 ADの治療─今までとこれから
- この数年で,AD治療は新時代に突入したと考えられる。新規外用薬が2剤登場し,各種生物学的製剤やJAK阻害薬などによる新規全身療法が登場した。
- かつての「ステロイド外用薬を塗っておけばよい」という時代は終焉し,それらの新規薬をいかに使いこなして患者のQOLを向上させていくかという時代に移行した。
1 はじめに
(1)アトピー性皮膚炎(AD)とは
アトピー性皮膚炎(atopic dermatitis:AD)は,増悪と軽快を繰り返す,かゆみを伴った湿疹を主病変とする疾患である。「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021」によると,有病率は乳児6~32%,幼児5~27%,学童5~15%,大学生5~9%となっており1),長期的には加齢とともに治癒傾向にある。
また,東京都が実施している3歳児調査におけるアレルギー性疾患の有症率の変化をみてみると,平成11年の16.6%に対して令和元年には11.3%となっており,この20年間で低下傾向を認める。この間に,ADと食物アレルギー(food allergy:FA)発症との関連性が指摘されるようになったことや,保湿剤によるAD発症予防効果が注目されたことで,医療者・保護者ともに乳幼児の湿疹に対する関心が強くなったことが要因かもしれない。
一方,乳幼児期に発症したADの7~8割が成人までに寛解するものの,学童期以降まで持ち越してしまった場合は寛解率が下がることが報告されている。そのため,乳幼児期にAD治療をしっかり行い,寛解を維持しておくことが,成人AD患者の「生きづらさ」を解消することにつながると思われる。
乳児期ADはアレルギーマーチの入口である。乳児期の“湿疹の向こう側”には,「アレルギーマーチ」とその後に「健やかな発達」があるという視点を持つことが必要である。
(2)新薬の登場
治療については,1999年のタクロリムス(プロトピックⓇ)軟膏発売以来,長らく新薬が登場していなかったが,2018年以降新規薬剤が次々と承認された。2021年3月に2歳以上の小児に対してデルゴシチニブ(コレクチムⓇ)軟膏が承認され,2023年1月に生後6カ月以上の小児に適応が拡大された。2021年9月に2歳以上の小児に対してジファミラスト(モイゼルトⓇ)軟膏が承認され,2023年12月に生後3カ月以上の小児に適応が拡大された。これにより,これまでステロイドに頼りきりだった外用療法にも選択肢が増えた。
また,既存治療では寛解させることができなかった重症例に対する全身療法も選択肢が増えてきた。特に小児科領域では,2023年9月にIL-4/IL-13受容体拮抗薬であるデュピルマブ(デュピクセントⓇ)が生後6カ月以上の小児に適応が追加されたことは,大きな転換点と言える。
これらの治療を組み合わせることによって,大きな副作用を経験することなく,日常生活にあまり支障がない状態を期待できると考えられ,AD治療は新時代に突入したと言えるだろう。
(3)かかりつけ小児科医の視点から
日本の医療制度では,ほぼすべての乳児が1カ月健診や2カ月のワクチンデビューで小児科医の診察を受けることになる。それをきっかけに,かかりつけ小児科医となる利点は,湿疹がある児を自ら探しに行く必要はなく,湿疹を主訴に来院するのを待つ必要もなく,ワクチン接種時に皮膚も診察すればよい,ということであろう。すなわち,かかりつけ小児科医こそが,アレルギーマーチの自然史に介入し,その後の健やかな発達を手助けするキーパーソンである。クリニックでプライマリ・ケアを担う小児科専門医・アレルギー専門医の立場から,小児ADを考察する。