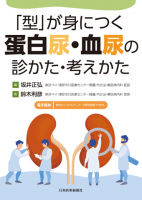お知らせ
膜性増殖性糸球体腎炎[私の治療]
膜性増殖性糸球体腎炎(membranoproliferative glomerulonephritis:MPGN)は病理組織診断に基づいた診断であり,特定の疾患を表したものではない。光学顕微鏡的所見でメサンギウム細胞増多,管内細胞増多,および糸球体係蹄壁の二重化を特徴とする。古典的には電子顕微鏡所見によりⅠ型,Ⅱ型,Ⅲ型に分類されていたが,現在は病態生理学的な観点から,①免疫グロブリン/免疫複合体介在型,②補体介在型,③免疫複合体・補体非介在型,に分類される。二次的に生じることが多いが,難病指定されている一次性MPGNもある。
▶診断のポイント
【症状】
発症様式は多彩であり,健康診断などで偶然に発見されるような無症候性血尿や蛋白尿などの検尿異常から,肉眼的血尿,急性腎障害やネフローゼ症候群を呈することもある。

【検査所見】
血尿,蛋白尿,腎機能障害に加え,免疫複合体介在型および補体介在型MPGNでは血清補体値の低値を認めることがある。
【組織学的所見】
MPGNは病理組織診断に基づいた診断であり,診断には腎生検が必須となる。
腎組織の光学顕微鏡的所見として,びまん性かつ全節性のメサンギウム細胞増多や管内細胞増多,細胞外基質増加に伴う分葉化,ならびに糸球体係蹄壁の肥厚や,メサンギウム間入による糸球体係蹄壁の二重化を特徴とする。時に半月体を認めることもある。
電子顕微鏡所見により,高電子密度沈着物がメサンギウム領域および内皮下に認められるⅠ型,糸球体基底膜内に認められるⅡ型,メサンギウム領域・内皮下に加えて上皮下にも認められるⅢ型,に分類される。Ⅱ型は特徴的な基底膜緻密層の連続性高電子密度沈着物が認められ,dense deposit disease(DDD)とも呼ばれる。
現在は免疫組織学的検査により,糸球体へ免疫グロブリン±補体が沈着する①免疫グロブリン/免疫複合体介在型,補体のみが沈着する②補体介在型,いずれも沈着しない③免疫複合体・補体非介在型,に分類されるようになってきている。補体介在型では,C3がメインに沈着するC3腎症が代表的であり,さらに電子顕微鏡所見により,C3腎炎とC3 DDDに分類される。

残り1,878文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する