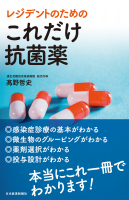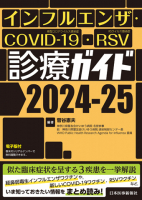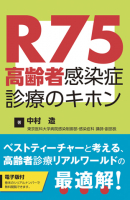お知らせ
フランスにおけるラッサ熱の輸入例の報告[感染症今昔物語ー話題の感染症ピックアップー(24)]
●ラッサ熱とは1)2)
ラッサ熱は,アレナウイルス科アレナウイルス属に分類されるラッサウイルスによるウイルス性出血熱です。1969年にナイジェリア北東部ボルノ州のラッサ総合病院(ラッサ村)で,修道女が死亡し,その患者の遺体に接触した医療従事者(病理解剖医を含む)も同様の症状を呈して死亡したときに初めて分離されました。
ラッサウイルスの宿主は中央〜西アフリカに分布するげっ歯類(マストミス;Mastomys natalensis)です。ヒトは,マストミスの尿や体液(ラッサウイルスが含まれる)に直接触れたり,経気道吸入したりすることにより感染します。潜伏期間は1〜3週間程度で,発熱,全身の痛み,嘔吐,下痢,粘膜からの出血が起こります。早期に,抗ウイルス薬(リバビリン)を使用することで致死率は低下しますが,有効なワクチンはありません。

日本では,感染症法で一類感染症に定められており,診断した医師は直ちに最寄りの保健所へ届け出ることが義務づけられています。日本でも1987年に1例のラッサ熱のシエラレオネからの輸入例が報告されています。詳細については,ナイジェリアにおけるラッサ熱のアウトブレイクについて紹介した本連載第21回(No.5214)を参照して下さい。
●フランスにおけるラッサ熱の輸入例の報告3)
2024年5月1日に,フランスの労働・保健・連帯省はラッサ熱確定症例の報告を受けました。患者は海外から帰国した兵士で,イル・ド・フランス地方に入院しており,健康状態は安定しています。2024年5月13日時点で,保健当局により詳細な疫学調査が行われ,患者との接触者の捜索を全力で行っています。
感染拡大防止のためには,接触者の調査・検査診断がきわめて重要であるため,本調査の結果が重要となります。
●ラッサ熱は,ウイルス性出血熱の中では,流行国以外にウイルスが持ち込まれるリスクが相対的に高い
日本では1987年にシエラレオネからの輸入例が報告されていますが,2000年以降,シエラレオネ,ナイジェリア,リベリアなどで感染し,ドイツ,英国,オランダ,米国でラッサ熱を発症した事例が報告されています。2016年3月にトーゴでの感染者がドイツ帰国後にラッサ熱を発症した事例が報告されています4)。さらにこの患者は死亡し,埋葬作業に携わった人もラッサウイルスに感染しました。
このように,世界的にみてもラッサ熱の非流行地での輸入事例は毎年のように報告されています。ラッサ熱は,ウイルス性出血熱の中でも輸入感染事例の報告数が最も多く,日本において一類感染症に指定されている5種類のウイルス性出血熱(エボラ出血熱,マールブルグ病,クリミア・コンゴ出血熱,ラッサ熱,南米出血熱)の中では,国内にウイルスが持ち込まれるリスクが相対的に最も高いと考えられます。そのため,発熱,嘔吐や下痢などの症状を認める場合,渡航歴の確認が重要です。海外との往来が活発になってきているため,診療の際には渡航歴を改めて確認しましょう。
【文献】
1)厚生労働省:ラッサ熱.(2024年5月13日アクセス)
3)フランス労働・保健・連帯省:イル・ド・フランス地方でのラッサ熱患者の確認. (2024年5月13日アクセス)
4)Ehlkes L, et al:Euro Surveill. 2017;22(39):16-00728.

石金正裕 (国立国際医療研究センター病院国際感染症センター/ AMR臨床リファレンスセンター/WHO協力センター)
2007年佐賀大学医学部卒。感染症内科専門医・指導医・評議員。沖縄県立北部病院,聖路加国際病院,国立感染症研究所実地疫学専門家養成コース(FETP)などを経て,2016年より現職。医師・医学博士。著書に「まだ変えられる! くすりがきかない未来:知っておきたい薬剤耐性(AMR)のはなし」(南山堂)など。