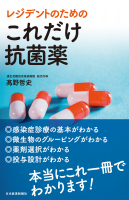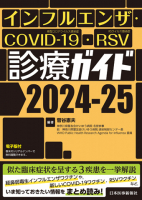お知らせ
感染性腸炎[私の治療]

急性の下痢や腹痛で発症する急性腸炎のうち,病原微生物を経口摂取することによる感染が原因となるものを感染性腸炎と言う。わが国では原因の80%以上がウイルス性で,ついで細菌性である。ウイルス性は冬に多く,ノロウイルスやロタウイルスが多い。主に小腸粘膜に感染し,発熱,腹痛,水様性下痢,嘔吐が主症状である。一方,細菌性は夏に多く,カンピロバクター, 腸炎ビブリオ,サルモネラ,赤痢菌,黄色ブドウ球菌,クロストリディオイデス・ディフィシル,下痢原性大腸菌などがある。主に回腸から大腸に感染することが多く,発熱や下痢,腹痛のほかに血便を伴うことがある。
下痢原性大腸菌のうち腸管出血性大腸菌(enterohemorrhagic Escherichia coli:EHEC)は血清型O157が最も多く,ベロ毒素を産生し腸管上皮細胞や血管内皮障害による血便や溶血性尿毒症症候群(hemolytic uremic syndrome:HUS),脳炎を合併することで重症化しやすい。
▶診断のポイント
腹痛,発熱など症状の程度や便の性状などから重症度を判断するとともに,食事摂取歴,海外渡航歴,周囲の感染者,服用薬剤,最近の抗菌薬使用歴などをできる限り詳細に聴取し,原因となる病原微生物を推定することが重要である。

採血で白血球高値かつ左方移動がみられる場合は主に細菌性を考慮し,一方でCRP高値にもかかわらず白血球高値や左方移動がみられない場合は主にウイルス性を考慮するが,基礎疾患や服用薬剤等の影響で必ずしも想定通りの採血結果にならないこともあり,注意が必要である。便培養や迅速診断キットも有用であるが,偽陰性になる例もあることに十分留意する。

残り1,299文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する