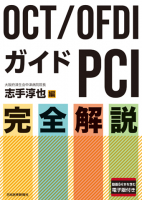お知らせ
学会レポート─2024年米国心臓病学会(ACC)[J-CLEAR通信(171)]
4月6日から3日間、米国アトランタにて米国心臓病学会(ACC)第73回学術集会が、ライブとオンラインで開催された。参加者総数は1万7367名、うち1万2756名が医療従事者だった。ここでは若干意外な結果と思われた大規模試験、また興味深い一般演題を紹介したい(4月上旬Web速報を整理)。
TOPIC 1
FFR陰性不安定プラークへのステント追加は薬剤治療単独に比べ虚血性心イベントを抑制?─RCT“PREVENT”
冠動脈狭窄を認めるものの、冠血流を著明低下させていない不安定プラークに経皮的冠動脈形成術(PCI)を施行すると、薬剤治療のみに比べ虚血性心イベントリスクが有意に低下する。エポックメイキングとも思われるランダム化比較試験(RCT)“PREVENT”が報告された。

しかし「PCI群では抗血小板薬併用やβ遮断薬服用率が有意に高い」「非盲検試験でハードエンドポイントに差がない」など、結果の解釈は難しそうだ。蔚山(ウルサン)大学校(韓国)のSeung-Jung Park氏の報告から紹介する。
【対象】
・導入基準等
PREVENT試験の対象は「冠動脈狭窄率≧50%」ながら「冠血流予備量比(FFR)≧0.80」、かつ血管内超音波(IVUS[グレーIVUSを含む])で不安定プラークを認めた日韓等在住の1606例である。ステント留置例や冠動脈バイパス施行例は除外されている。年齢中央値は65歳、女性は27%だった。虚血性心疾患の内訳は「安定狭心症/無症候性心筋虚血」が最多の84%、次いで「不安定狭心症」12%、「心筋梗塞(MI)」4%だった。
【方法】
これら1606例は至適薬剤治療を受けた上で、PCI「追加」群と「非追加」群にランダム化され、非盲検下で観察された。1次評価項目は「心臓死・標的血管MI・心筋虚血を端緒とする標的血管血行再建・狭心症増悪/不安定狭心症による入院」である。
PCIには当初、生体吸収型ステント(Absorb®)を用いたが発売中止となったため、エベロリムス溶出ステント(XIENCETM)が使用された。なおPCI「追加」群では施行6~12カ月間、必要に応じて抗血小板薬併用(DAPT)を実施した。
【結果】
・抗血栓薬/心保護薬服用状況(論文付録から引用)
試験開始から終了時まで、DAPT服用率は一貫してPCI「追加」群で多かった。2年目終了時の数字は35.9% vs. 16.8%である。同様にβ遮断薬服用率も「追加」群で若干だが有意に高かった(1年目は60.3% vs. 53.9%、2年目も60.0% vs. 53.3%)。
一方、硝酸薬とカルシウム拮抗薬、レニン・アンジオテンシン系阻害薬の服用率には差を認めなかった。
・1次評価項目
2年間の観察期間後、「心臓死・標的血管MI・心筋虚血を端緒とする標的血管血行再建・狭心症増悪/不安定狭心症による入院」発生リスクは、PCI「追加」群で著明かつ有意に減少していた。
すなわち、対「非追加」群ハザード比(HR)は0.11(95%信頼区間[CI]:0.03-0.36)、発生率は「追加」群が0.4%、「非追加」群で3.4%だった(なお試験設計時に想定していたイベント発生率は「追加」群が8.5%、「非追加」群で12.0%)。この両群間の差は、7年間観察できた131例で比較しても維持されていた。
ただし細かく見ると、2年間の「心臓死」と「標的血管MI」発生率は、PCI「追加」群で低いものの「非追加」群に対して有意差とはならなかった。群間差はいずれも0.6%である。
一方、「心筋虚血を端緒とする標的血管血行再建」と「狭心症増悪/不安定狭心症による入院」には有意差がついた。2年間の発生リスク差は前者が2.3%、後者で1.4%だった。
・安全性
大出血の2年間発生率は,PCI「追加」群が0.6%で、DAPT施行率が高いにもかかわらず「非追加」群(1.4%)より低値だった(有意差とはならず)。
【考察】
パネルディスカッションでは「本当に不安定プラーク例が選ばれているのか」との問いが出された。パネラーはグレーIVUSを用いた「不安定性」評価の信頼性に疑問を感じているようだった。Park氏は直接これに答えなかったが、プラーク不安定性評価のモダリティ選択を現場に任せた点を本試験の限界の1つとして挙げていた。
本試験は以下から資金提供を受けた。The Cardio Vascular Research Foundation、Abbott、Yuhan Corp、CAH-Cordis、Philips、Infraredx、Nipro company。
また報告と同時に論文がLancet誌ウェブサイトで公開された1)。
TOPIC 2
急性MI後HF高リスク例に対するSGLT2阻害薬は「死亡・HF初回入院」を減少せず ─RCT“EMPACT-MI”
慢性心不全(HF)の50%は虚血性心疾患を合併しており(2002〜14年コホート)2)、心筋梗塞(MI)後のHF発症抑制は現在でも重要な課題である。そこで期待されたのがSGLT2阻害薬だが、ランダム化比較試験(RCT)“EMPACT-MI”では「死亡・HF初回入院」を抑制できなかった。ベイラー・スコット&ホワイト医療センター(米国)のJaved Butler氏が報告した。
なお上記1次評価項目に有意差はないものの、「HF(初発)入院」のみで比較するとSGLT2阻害薬群で著明かつ有意な減少が認められた。この点をどう評価するかが、今後の焦点になりそうだ。
【対象】
・導入/除外基準
EMPACT-MI試験の対象は、MI後搬送から14日以内で、標準治療にもかかわらずHF発症高リスクだった6522例である。具体的には「左室駆出率(EF)低下」(<45%)、あるいは「加療を要するうっ血」を呈し、加えてそれ以外にもHF発症リスク因子を有していた例である。日本を含む世界22カ国の451施設から登録された。
MIはST上昇の有無を問わない。またHF既往例は除外されている。「実臨床でも用いうる導入/除外基準だ」とButler氏はコメントしている。
ただしDeep Diveセッションで本試験を論じたデューク大学(米国)のRobert Mentz氏は、本当にHF高リスク例のみが登録されたのか疑義を呈している。この基準では冬眠心筋例なども含まれていた可能性があるという。
・患者背景
患者背景を見ると、ST上昇型MI(STEMI)が74.3%を占め、男性の割合が75.1%、65歳以上は50.0%だった。また6522例中36%では「うっ血」と「EF<45%」が併存しており、「EF低下」のみが43%、「うっ血」のみは21%だった。
・MI治療
MIに対しては十分な治療が実施されていた。すなわち急性期には89.3%で再灌流療法が実施され、心保護薬も退院時までに86.7%がβ遮断薬、82.5%がレニン・アンジオテンシン系阻害薬を服用、ミネラルコルチコイド阻害薬服用率も47.8%に達した。またスタチンは95.3%が服用、抗血小板薬服用率は98.1%だった。
【方法】
これら6522例はMIへの標準治療継続の上、SGLT2阻害薬(エンパグリフロジン10mg/日)群とプラセボ群にランダム化され、二重盲検法で観察された。
1次評価項目は「死亡とHF初回入院」である。本試験は「簡略化」を旨としており、イベントの中央検証は実施せず、各施設で治療を盲検化された研究者が判定することにした。そのような環境で正確に評価できるよう、このような評価項目が選ばれたという。
【結果】
・1次評価項目
その結果、1次評価項目である「死亡とHF初回入院」リスクに両群間で有意差はなかった。17.9カ月間(中央値)における発生率は、SGLT2阻害薬群で5.9%/年、プラセボ群で6.6%/年。SGLT2阻害薬群におけるハザード比(HR)は0.90(95%信頼区間[CI]:0.76-1.06)だった。
なおこの発生率を、指定討論者であるマサチューセッツ総合病院(米国)のJames Januzzi氏は(良い意味で)「想定よりもかなり低い」と評した。ただし本試験におけるイベント数は、試験設計時の想定数に達しており、検出力に問題はない。
一方、「HF初回入院」(1次評価項目中48%)のみで比較すると、SGLT2阻害薬群でリスクは有意に低くなっていた。同群の発生率は2.6%/年。プラセボ群の3.4%/年に比べ、HRは0.77(95%CI:0.60-0.98)である。両群の発生率曲線は試験開始後90日を待たずに乖離を始め、群間差の経時的減弱は認めなかった。またHF「初回」入院に限らず「全HF入院」で比較しても、SGLT2阻害薬群における有意なリスク低下が認められた。
対照的に、1次評価項目の52%を占めた「死亡」では、試験開始810日後に至るまで両群の発生率曲線は一貫して乖離の兆しもなく、ほぼ重なり合ったまま推移した(HR:0.96、95%CI:0.78-1.19)。HF(初回)入院抑制が生存率改善に結び付かなかった理由をButler氏は、「観察期間が短いため」と述べた。
他方、前出のMentz氏はDeep Diveセッションにて、SGLT2阻害薬が介入できない機序による死亡(虚血性心疾患死や不整脈死など)が関連した可能性を指摘した。なお同セッションにおけるButler氏の発言によると「HF関連死」はSGLT2阻害薬群で相対的に29%、有意なリスク低下を観察したという。
・安全性
重篤な有害事象発現はSGLT2阻害薬群とプラセボ群間に差はなかった。急性腎不全も同様だった。
【考察】
今回示されたSGLT2阻害薬による「HF入院減少」は1次評価項目ではない。しかし他試験データとの一貫性を考慮すれば「MI後にSGLT2阻害薬を使えばHFを抑制しうる」とButler氏は述べた。
ただし,SGLT2阻害薬の有用性は非ST上昇型MI(NSTEMI)例のほうが大きかったということで(データ提示なし)、Deep Diveセッションでは「NSTEMIならSGLT2阻害薬を考えるが、STEMIだったら経過を観察する」とも発言していた。
なお記者会見では指定討論者だったブリガム・アンド・ウィミンズ病院(米国)のPatrick O’Gara氏がDAPA-MI試験3)との違いに言及した。昨年の米国心臓協会(AHA)で報告された同試験では、MI後SGLT2阻害薬開始による転帰改善win ratioはプラセボに比べ有意に高かった。一見すると今回の結果と対照的にも映る。しかし、DAPA-MI試験で認められた差は「新規2型糖尿病発症抑制」と「体重減少」に負うところが多く、「心臓血管系死亡・HF入院」発生率は、EMPACT-MI試験同様、SGLT2阻害薬群とプラセボ群間に差はなかった。
EMPACT-MI試験はBoehringerIngelheim(BI)とEli Lillyから資金提供を受けて実施された。また複数のBI社員が治験運営委員を務め、統計解析もBI社員が実施した。
本試験は報告と同時にNEJM誌ウェブサイトで公開された4)。
TOPIC 3
MI後「EF≧50%」例へのβ遮断薬は「死亡・MI入院」を抑制せず、再灌流療法時代に入り再検討の必要性も─RCT“REDUCE-AMI”
心筋梗塞(MI)後に必須とされているβ遮断薬だが、左室駆出率(EF)「≧50%」例ではその後の心イベントは減少しないとの観察研究がある5)。そしてランダム化比較試験(RCT)でも、同様の結果となった。ルンド大学(スウェーデン)のTroels Yndigegn氏が“REDUCE-AMI”試験の結果として報告した。
【対象】
REDUCE-AMI試験の対象は、MI発症から1~7日後で「EF≧50%」だった5020例である。他疾患でβ遮断薬の適応がある例は除外されている。スウェーデンとエストニア、ニュージーランドの45施設から登録された。
・患者背景
年齢中央値は65歳、女性は22.5%のみ。MI類型はST上昇型MI(STEMI)が36%だった。
MIに対する治療は十分に実施されていた。すなわち経皮的冠動脈形成術(PCI)施行率は95%、β遮断薬以外の心保護薬服用率は、退院時、レニン・アンジオテンシン系阻害薬が80%、スタチンは98%だった。また97%がアスピリン、96%がP2Y12阻害薬を服用していた。
【方法】
これら5020例はMI後標準治療を継続した上で、登録施設単位でβ遮断薬「服用」群と「非服用」群にランダム化され、非盲検で観察された。β遮断薬の種類と目標用量は、メトプロロール100mg/日またはビソプロロール5mg/日である。
【結果】
・有効性
1次評価項目である「全死亡・MI入院」の発生リスクは、中央値3.5年間の観察期間後、「服用」群と「非服用」群間に有意差を認めなかった。すなわち「服用」群におけるハザード比は0.96(95%信頼区間[CI]:0.79-1.16)、発生率は「服用」群が7.9%、「非服用」群は8.3%だった(発生率は当初想定より低かったが、予定通りのイベント数は確保)。この結果は、「服用」群を目標用量「達成」群と「非達成」群に分けた後付解析でも同様だった(スウェーデンデータのみ。Deep Diveセッションにて報告)。
全体で評価した2次評価項目も同様で、「心不全入院」「心房細動入院」にも有意差はなかった。またβ遮断薬「服用」が有用と思われる亜集団も存在しなかった。
・安全性
安全性にも両群間に差はなかった。徐脈や失神、慢性閉塞性肺疾患入院、脳卒中のいずれも「服用」群におけるリスク上昇は認めなかった。
【考察】
Yndigegn氏は本研究について3つの限界を指摘した。
まず追跡は非盲検だった。加えて本試験の臨床イベントは、参加施設からの報告がそのまま採用されており、独立した委員会によるチェックは受けていない(PROBE法になっていない)。
またクロスオーバーも多かった。スウェーデン登録4788例のみのデータだが、「非服用」群にもかかわらず11.3%がβ遮断薬を試験開始8カ月後には服用し、12カ月後ではこの数字が14.3%まで増えていた。「プロトコル遵守群解析」を実施したいところだが、エストニアとニュージーランドはアドヒアランス情報がなく、スウェーデンでも1年以降はデータがないため、不可能だという。
一方、Deep Diveセッション指定討論者であるニューヨーク大学(米国)のSripal Banglalore氏は、現代におけるMI後β遮断薬の有用性そのものに疑義を呈した。曰く、MI後β遮断薬の有用性を示した臨床試験はすべて、再灌流療法が一般的となる以前のものであり、再灌流療法時代にMI後β遮断薬を検討したRCTのメタ解析では有用性は認められていない6)。「治療の進歩に伴う背景リスクの変化に応じて、古い治療は見直す必要がある」と同氏は結んだ。
本試験はSwedish Research Councilなどから資金提供を受けた。製薬会社からの資金提供はない。また報告と同時にNEJM誌ウェブサイトで公開された7)。
TOPIC 4
「コレステロール逆転送」増強はまたもCVイベントを抑制せず、ただし有望な亜集団が存在する可能性も─RCT“AEGIS-Ⅱ”
「善玉コレステロール」とされるHDL-Cだが、その増加がアテローム性動脈硬化によるイベントを減らすというエビデンスはない。フィブラート、CETP阻害薬はいずれも、それらイベントを抑制しなかった8)。ただし「コレステロール逆転送」能が不十分だった可能性も指摘されている。
そこで注目されたのが、「逆転送」亢進作用が既に報告されている9)「(ヒト)アポA1製剤」(CSL112)である。ランダム化比較試験(RCT)“AEGIS-Ⅱ”において、心筋梗塞(MI)後例の心血管系(CV)転帰作用がプラセボと比較された。
しかしやはり、有意な抑制作用は認められなかった。ハーバード大学(米国)のC. Michael Gibson氏が報告した。
なお、LDL-Cが十分に低下していない例では有用性を示唆するデータも得られており、今後の展開も注目される。
【対象】
AEGIS-Ⅱの対象は、MI発症後5日間以内で、多枝病変とCVリスク因子を認めた1万8219例である。49カ国の886施設から登録された。
・背景因子
平均年齢は66歳、男性が74%を占めた。MIはST上昇型(STEMI)と非ST上昇型(NSTEMI)がほぼ半数ずつで、88%が経皮的冠動脈形成術(PCI)を施行されていた。
MIに対する薬剤治療は、スタチン、アスピリン、その他抗血小板薬のいずれも服用率は93%と高かった。また試験開始時のLDL-C中央値は84mg/dL、HDL-Cが39mg/dLだった。
【方法】
これら1万8219例は「アポA1製剤」静注群と「プラセボ」静注群にランダム化され、最長365日間、二重盲検法で観察された。「アポA1」「プラセボ」とも「週1回」静注を4週続けて実施した。
【結果】
・主解析
その結果、1次評価項目である90日間「CV死亡・MI・脳卒中」リスクに、両群間で有意差はなかった(イベント数に不足はなし)。すなわち「アポA1製剤」群におけるハザード比(HR)は0.93(95%信頼区間[CI]:0.81-1.05)である。観察期間を180日間、365日間と延長して解析しても同様で、有意な群間差には至らなかった。またいずれのサブグループも、90日観察時点では両群間に有意差を認めなかった。
・探索的(後付)解析(NEJM未掲載)
一方、開始時LDL-C値の高低で2群に分けた探索的解析は興味深い結果となった。
すなわちスタチン服用下でLDL-C値「<100mg/dL」だった1万427例では、「アポA1製剤」群と「プラセボ」群間に「CV死亡・MI・脳卒中」リスクの差はほぼ皆無だった一方、LDL-C値「≧100mg/dL」だった5304例では「アポA1製剤」群における有意なリスク低下が観察された。
具体的には、90日後HRが0.69(95%CI:0.53-0.90)、180日後も0.71(0.57-0.88)、365日後が0.78(0.65-0.93)である。「アポA1製剤」群と「プラセボ」群の発生率曲線乖離は、試験開始後45日を待たずに始まっていた。同様の差は「CV死亡」「MI」のみで解析しても認められた。
【考察】
本試験はネガティブだったが、アポA1製剤は安全性にも特に問題がなかったためGibson氏は、LDL-C高値例のみを対象としたRCTを組む価値があると考えている。
なお指定討論者として登壇したAnn Marie Navar氏は「LDL-C≧100mg/dL」例サブ解析を過信せぬよう注意を促した。根拠のひとつはフィブラートを用いたRCTだ。複数のサブグループ解析が、低HDL-Cを呈する高トリグリセライド血症例におけるCVイベント抑制作用を示していた10)が、前向きに検討したRCT“PROMINENT”はネガティブだった11)。そのためGibson氏同様、新たなRCTで確認する必要性を唱えている。
本試験はCSL Behringから資金提供を受けて実施された。また報告と同時にNEJM誌ウェブサイトで論文が公開された12)。
TOPIC 5
SGLT2阻害薬のHFpEFエビデンスが当てはまる患者は4割以下、NT-pro BNPがネックに─スペイン観察研究
左室駆出率が保たれた心不全(HFpEF)に対して、死亡や心血管系(CV)死亡は減少しないものの転帰改善作用が示されているSGLT2阻害薬だが、エビデンスとなったランダム化比較試験(RCT)“EMPEROR-Preserved(P)”13)や“DELIVER”14)の結果が当てはまる患者は実臨床にどれほどいるのだろう。スペイン単施設における連続登録例で検討したところ37%という結果だった。マーストリヒト大学(スペイン)のJerremy Weerts氏が報告した。
【対象】
解析対象となったのはスペイン単施設でHFpEFと診断された連続登録438例である。年齢中央値は76歳、女性が69%を占めた。左室駆出率中央値は60%、左房容積係数中央値は45mL/m2だった。
【方法】
これら438例におけるEMPEROR-PとDELIVERでの参加可能(=適格)例の割合を調べた。
【結果】
その結果、EMPEROR-Pに「適格」だったのは23%、DELIVERも27%だった(いずれにも「適格」の13%を含む)。一方、63%はいずれの試験にも「不適格」だった。
「不適格」の理由として最多だったのは「NT-pro BNP基準未達成」で、「不適格」例のうちEMPEROR-Pでは55%、DELIVERでは37%を占めた。両試験ともNT-pro BNP基準は「>300pg/mL」とされていた(心房細動例は「>900pg/mL」)。
なお「NT-pro BNP」の中央値を比較すると、全体では582pg/mL、EMPEROR-Pの「適格」例では1476pg/mL、DELIVERの「適格」例では1116pg/mLだった。一方、いずれの試験にも「不適格」だった63%における中央値は324pg/mLである。
本研究に関し、開示すべきCOIはないとのことである。
TOPIC 6
CV 1次予防例ではケトン体高値でCV転帰増悪─UK Biobank
SGLT2阻害薬による心保護作用の一機序と考えられている血中ケトン体濃度上昇だが15)、心不全(HF)や心血管系(CV)疾患がない例ではCV転帰を増悪させる可能性がある。ウェイクフォレスト大学(米国)のParag Anilkumar Chevli氏が、大規模観察データの結果として報告した。
【対象】
Chevli氏らが解析対象としたのは、アテローム性動脈硬化性CV疾患(ASCVD)、HFいずれも有さない英国住民9万987例である。自主参加型コホート研究“UK Biobank”から抽出した。平均年齢は56.4歳、女性が54.7%を占めた。
【方法】
これら9万987例の、観察開始時のケトン体量(NMRスペクトロスコピーで評価)と、その後のASCVD、HF発症リスクを比較した。比較にあたっては、以下の背景因子を補正した(年齢、性別、人種、経済状況、肥満度、糖尿病の有無、喫煙の有無、血圧、総コレステロール、HDL-C、スタチン服用の有無、腎機能、アルコール摂取、身体活動性)。
【結果】
平均13.8年間の観察で、6.2%がASCVDを、3.2%がHFを発症した。観察開始時ケトン体量10倍増に伴うハザード比は、ASCVDが1.32(95%信頼区間[CI]:1.19-1.47)、HFも1.50(95%CI:1.30-1.74)だった。
また開始時ケトン体量三分位数で分けても、「最低」群に比べ「第二」「最高」群ではASCVD、HFとも発生率が高い傾向を認めた(検定不記載)。
【考察】
Chevli氏らは、ケトン体量をCV高リスク群のスクリーニングに用いうるのではないかと考察している。なおCV 1次予防例におけるケトン体量上昇に伴うCVイベント多発は、米国大規模コホートからも報告されている16)。
本研究はCOIに関する開示がなかった。
TOPIC 7
“Life Essential 8”遵守で乳癌サバイバーの動脈硬化性イベント著減? ─“Women’s Health Initiative”解析
がん治療の心血管系(CV)リスクとしては心不全に注目が集まるが、アテローム性動脈硬化に起因する虚血性イベントリスクも著増する17)。しかしこのリスクは、「血圧」「血糖」「血清脂質」管理と生活習慣改善だけで大幅に低減できる可能性が明らかになった。ワシントン大学(米国)のElena Wadden氏が米国の大規模前向きコホート解析の結果として報告した。
【対象】
Wadden氏らが解析したのは、乳癌治療歴のある米国医療従事者7165例である。前向きコホート研究“Women’s Health Initiative”から抽出した。乳癌診断時の平均年齢は70.1歳、BMI平均値は28.4kg/m2だった。
【方法】
これら7165例を、乳癌診断前の“Life Essential 8”(LE8)スコアの高低別に分け、診断後CVイベントリスクを比較した。
LE8スコアとは、米国心臓協会(AHA)が提唱している「CV系健康維持のために重視すべき指標」である8項目(LE8)を5~7段階に分け、達成度をポイント化したものである18)。高値ほど達成度は高い。
8項目の内訳は「血圧」「HbA1c」「非HDL-C」「喫煙状況」「BMI」「身体活動活発度」「食事健康度」「睡眠時間」である。
このLE8スコアで7165例を「低」「中」「高」の3群に分け、「冠動脈疾患死・心筋梗塞・脳卒中」(動脈硬化性イベント)リスクを比較した。
【結果】
中央値6.0年の観察期間中、6.8%で動脈硬化性イベントが発生した。LE8スコア別に10年発生率を計算すると、「高」が1.5%、「中」9.1%、「低」では16.2%となった。3群のイベント発生率曲線乖離は、観察期間を通じて拡大し続けていた。
次に諸因子を補正してハザード比(95%CI)を算出した。するとLE8スコア「中」「高」群とも、「低」群に比べ著明かつ有意に低値となっていた。すなわち、「中」群で0.62(0.50-0.77)、「高」群は0.42(0.25-0.73)である。
また「LE8」スコア「10ポイント」高値に伴い、動脈硬化性イベント相対リスクは18%、有意に低下していた。なおLE8個別項目の中では、「喫煙状況」と「血糖」「血圧」の3つが、「動脈硬化性イベント」との相関が強かった。
【考察】
Wadden氏らは、LE8達成が乳癌既往例のCV疾患予防に有用ではないかと考察し、ランダム化比較試験など、さらなる検討が必要だと考察していた。
本研究は米国心肺血液研究所、ならびに保健福祉省から資金提供を受けた。
TOPIC 8
実臨床におけるセマグルチドの減量作用はどれほど? ─米国大規模観察
わが国でも減量治療への使用が始まったGLP-1受容体作動薬セマグルチドだが、実臨床において5%を超える減量が期待できるのは約半数のようだ。ヒューストン・メソジスト病院(米国)のEleonora Avenatti氏が報告した。同氏によれば、セマグルチドによる減量作用を検討した実臨床データとしては、現在公表されている中で最大級だという。
【対象】
解析対象となったのは、米国ヒューストンに在住でセマグルチド注を開始した「BMI≧27kg/m2」の3万3773例である。2型糖尿病(DM)の有無は問わない。同地における心血管系(CV)疾患検討レジストリから抽出した。
【方法】
セマグルチド開始後の減量幅、減量率を観察した。観察期間中央値は323日だった。
【結果】
セマグルチド開始後に「5%超」の減量が見られたのは、「0.25-0.5mg/週」(低用量)で26.2%、「1.0-1.7mg/週」(中等用量)で38.7%、「2.0-2.4mg/週」(高用量)で53.0%だった。「10%超」減量に基準を引き上げると、達成率は順に10.0%、17.1%、27.5%である。
2型DMを合併していると減量作用が減弱する傾向も見られた。すなわち、セマグルチド高用量で「5%超」減量達成率を比べると、非DM例では61.4%だったのに対し、DM合併例では47.6%だった(検定不詳)。この数字を「10%超」減量で比較すると「35.3%(非DM) vs. 22.5%(DM)」となる。
なおセマグルチド使用開始前BMIの高低は、使用開始後の体重減少率に影響を与えていないようだった(検定不詳)。
【考察】
実臨床におけるセマグルチドの減量作用はランダム化比較試験で報告されているほど強くないと、Avenatti氏らは結論している。
本研究に開示すべきCOIはないとのことである。
【文献】
1)Park SJ, et al:Lancet. 2024;403(10438):1753-65.
2)Conrad N, et al:Lancet. 2018;391(10120):572-80.
3)James S, et al:NEJM Evid. 2024;3(2):EVIDoa 2300286.
4)Butler J, et al:N Engl J Med. 2024;390(16):1455-66.
5)Joo SJ, et al:Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2021;7(6):475-82.
6)Bangalore S, et al:Am J Med. 2014;127(10):939-53.
7)Yndigegn T, et al:N Engl J Med. 2024;390(15): 1372-81.
8)Keene D, et al:BMJ. 2014;349:g4379.
9)Gille A, et al:Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014; 34(9):2106-14.
10)Pradhan AD, et al:Am Heart J. 2018;206:80-93.
11)Pradhan AD, et al:N Engl J Med. 2022;387(21): 1923-34.
12)Gibson CM, et al:N Engl J Med. 2024;390(17): 1560-71.
13)Anker SD, et al:N Engl J Med. 2021;385(16): 1451-61.
14)Solomon SD, et al:N Engl J Med. 2022;387(12): 1089-98.
15)Cowie MR, et al:Nat Rev Cardiol. 2020;17(12): 761-72.
16)Shemesh E, et al:Eur Heart J. 2023;44(18):1636-46.
17)Galimzhanov A, et al:Eur J Prev Cardiol. 2023;30 (18):2018-31.
18)Lloyd-Jones DM, et al:Circulation. 2022;146(5): e18-43.