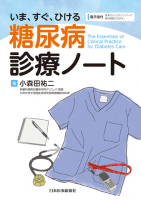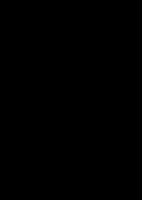お知らせ
■NEWS 心血管疾患の危険因子「Lp(a)」の国際標準化、日本主導で推進─動脈硬化学会・三井田理事

日本動脈硬化学会(JAS)の三井田孝理事(順天堂大医療科学部臨床検査学科特任教授)は2月14日、同学会が開いたメディア向けセミナーで講演し、動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)の危険因子として注目されているLp(a)〔リポ蛋白(a)〕について、日本主導で測定値の国際標準化を進める考えを強調した。
Lp(a)は、いわゆる悪玉コレステロールのLDLとは独立した、動脈硬化を促進するリポ蛋白。スタチンなどでLDLコレステロールを強力に下げても残余リスクがあることから、ノバルティスのPelacarsenをはじめ製薬メーカー各社がLp(a)を低下させる薬剤の開発を進めており、2~3年後の臨床での実用化が期待されている。

Lp(a)が高値であるほどASCVDのリスクが高まることは国際的なコンセンサスとなっており、米国のAHA/ACCガイドライン2019はLp(a)値50㎎/dL以上を「ASCVDのリスク増強因子」、欧州のESC/EASガイドライン2020も50㎎/dL以上を「ASCVDのハイリスク群」と記載。一方、JASの動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022は、Lp(a)について「考慮すべき危険因子・バイオマーカー」と記載するにとどめている。
■「臨床系学会を巻き込んで一気に進めたい」
講演で三井田氏は、JASガイドラインの次回改訂時(2027年)にLp(a)値について言及するには「(測定値の)標準化が必要」と指摘。
Lp(a)は構造の多様性のため、検査キット間で測定値の差が大きいことが問題となっているが、国際臨床化学連合(IFCC)が公認した方法で補正するとキット間差が大幅に縮小することが分かってきたとし、現在、日本臨床検査医学会、日本臨床化学会などの合同プロジェクトでLp(a)の国際標準化の検討を進めていることを説明した。
また、Lp(a)の分子量は正確に知ることができないため、Lp値を「㎎/dL」で表示するのは「計量学的な誤り」だとし、国際標準化と同時にSI単位(nmol/L)への移行も必要と指摘した。
三井田氏は、2025年中には合同プロジェクトの結果発表があり、JASからLp(a)のコンセンサスステートメントが出されるとの見通しを示しながら、「検査系学会と臨床系学会が連携して国際標準化とSI単位への移行を我が国がリードして世界的に進めていきたい」と強調。
「循環器病学会や糖尿病学会などを巻き込んで国際標準化を一気に進めなくてはいけない。日本だけでなく、アジアやヨーロッパなど海外の人たちも巻き込んで進めていきたい」と意欲を示した。
「Lp(a)の国際標準化とSI単位への移行が必要」と強調する三井田氏