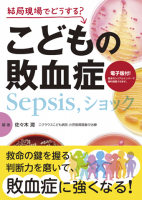お知らせ
極低出生体重児の発達障害【救命率の向上によりリスク児も増加傾向】
未熟児医療の進歩により,極低出生体重児の救命率が飛躍的に改善している中,極低出生体重児では,発達障害の問題を持つ患者が正期産児に比して多いという報告が相次いでいる。これらからは,自閉スペクトラム症(ASD)の発生頻度が高いこと,注意欠陥・多動性障害では不注意症状が主体であること,学習障害では読字,算数,書字などのうち2つ以上の複数領域にわたる障害の存在が特徴であること,が報告されている。一般的に発達障害の児では3歳くらいから明らかになり,集団適応の問題が生じ医療機関への相談につながる。しかし,極低出生体重児の多くは,低年齢よりフォローアップ健診が行われていることもあり,1歳半過ぎより発達の問題に気づかれることが少なくない。筆者らのフォローアップ外来では,このようなリスク児に対しては家庭での母子コミュニケーションの確立を促進するような遊びなどを提案する一方,地域の発達または療育センターなどを紹介し,療育を開始することを勧めている。そして5,6歳には一般の幼稚園も併用して通園することなどを提案し,社会性の発達を促す。
今後さらに増えると思われる極低出生体重児の診療においては,発達障害の存在を考慮して,ASDのスクリーニングのためにmodified checklist for autism in toddlers(M-CHAT)などを積極的に取り入れ,リスク児に対して早期の療育介入を提案している。発達のつまずきを持つことで過剰に不安を抱き,母子関係を築くことができない親子に対して,情報提供や生活習慣確立のためのサポートを積極的に行っていくことも,我々小児科医に求められている。

【解説】
平澤恭子 東京女子医科大学小児科准教授