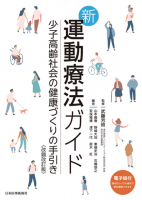お知らせ
(2)高齢心疾患患者に対する運動機能評価と運動療法の実際[特集:心臓リハビリテーションの進め方]
No.4974 (2019年08月24日発行) P.27
高橋哲也 (順天堂大学保健医療学部教授)
森沢知之 (順天堂大学保健医療学部准教授)
藤原俊之 (順天堂大学大学院医学研究科リハビリテーション医学研究室主任教授)
横山美帆 (順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学)
島田和典 (順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学先任准教授)
代田浩之 (順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学特任教授)
登録日: 2019-08-26
最終更新日: 2019-08-21

運動負荷試験が実施できない高齢患者であっても,運動機能の客観的評価に基づく運動プログラムの作成に努めなければならない
高齢心疾患患者には生活機能向上を意識した運動療法を行う

フレイルは心疾患の発症や再入院など予後にも強く影響する
高齢心不全患者の特徴である動作の緩慢性,低体力,バランス機能の改善を目的に運動療法をプログラムする
各運動機能のレベルに応じた課題特異的な運動療法プログラムを処方する
1. 心臓リハビリテーションの定義と運動機能評価
わが国の心臓リハビリテーション(以下,心リハ)の定義は,「心血管疾患患者の身体的・心理的・社会的・職業的状態を改善し,基礎にある動脈硬化や心不全の病態の進行を抑制あるいは軽減し,再発・再入院・死亡を減少させ,快適で活動的な生活を実現することをめざして,個々の患者の“医学的評価・運動処方に基づく運動療法・冠危険因子是正・患者教育およびカウンセリング・最適薬物治療”を多職種チームが協調して実践する長期にわたる多面的・包括的プログラムをさす」1)とされており,運動機能に加え,精神心理機能,社会的生活機能の重要性を包含し,加えて,再発や再入院の予防(二次予防)や長期予後改善を含む包括的管理プログラムとして知られている。
この包括的管理プログラムの中でも,運動機能を改善する運動療法は,心リハの中心的プログラムであり,これまでにも多くのエビデンスの蓄積がなされてきた2)。そして,運動療法を医学的に処方するための運動負荷試験が,心リハにおける運動機能の評価のメインでもある。運動処方を目的とした運動負荷試験には,トレッドミルエルゴメータや自転車エルゴメータを用いた運動負荷試験,特に呼気ガス分析を併用した心肺運動負荷試験(cardiopulmonary exercise testing:CPX)がわが国では主流となっている。
一方,社会の高齢化に伴う対象患者の変化は顕著で,トレッドミルエルゴメータや自転車エルゴメータを用いた運動負荷試験が実施できない高齢患者が増加している。心リハの定義で,「運動処方に基づく運動療法」が明記されている関係上,CPXができない場合であっても,日常生活の実現に必要である基本的な運動機能を医学的に評価し,その客観的評価結果に基づく,運動プログラムの作成に努めなければならない。