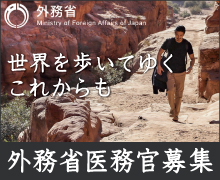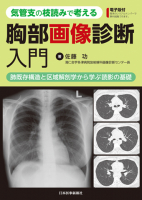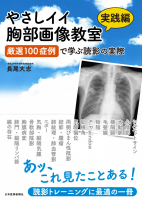お知らせ
「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019」を読み解く①
【成人遷延性・慢性咳嗽への対応の手順について】
「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019」が2019年4月に上梓された1)。

内科診療において受診のきっかけとなる症候として最も多いのが咳である。特に「長引く咳」には様々な原因疾患があり,診断に苦慮することが少なくない。本ガイドラインで巻頭フローチャートとして取り上げられている成人の遷延性・慢性咳嗽への対応の手順を紹介する。
咳嗽は,持続している期間により原因疾患が異なるため,3週間未満の急性咳嗽,3週間以上8週間未満の遷延性咳嗽,8週間以上の慢性咳嗽に分類することは,原因疾患を診断するプロセスにおいて非常に重要となる。急性咳嗽の原因として頻度が高いのは気道感染症であり,ほとんどがウイルス性の普通感冒である。遷延性咳嗽では感染症の頻度が減少し,さらに慢性咳嗽になると感染症以外の原因が主となる。
胸部X線写真と胸部聴診で異常を認めない成人の遷延性・慢性咳嗽の原因として,喀痰がある場合は副鼻腔気管支症候群の可能性が高く,喀痰がないか,あっても少量または一過性の場合は咳喘息,アトピー咳嗽/喉頭アレルギー,胃食道逆流症,感染後咳嗽を疑う。さらに,診断的治療の方法が示されており,非専門医が診断を導き出せるような配慮がなされている。ただし,診断や治療に難渋する場合は,専門医への紹介を考慮すべきである。
【文献】
1) 日本呼吸器学会:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019. メディカルレビュー社, 2019.
【解説】
金子 猛 横浜市立大学呼吸器病学主任教授/日本呼吸器学会「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019」作成副委員長,喀痰セクション責任者