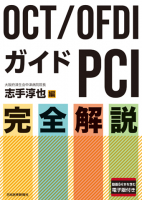お知らせ
古薬に良薬あり─コルヒチンの心血管リスク低減作用[J-CLEAR通信(122)]

はじめに
至適内科治療(optimal medical treatment:OMT)という言葉がある。冠動脈疾患は代表的な複合因子的な疾患である。喫煙,高血圧,糖尿病,脂質異常症など様々な因子が複合的に作用して疾病が形成される。こうした疾病に対しては関係すると思われる諸因子を逐次徹底的にコントロールすることにより,疾病の一次・二次予防を図るやり方が考えられ,OMTと呼ばれた。冠動脈疾患に対しては1990年代の半ばから2000年代初めに確立されたといえる。冠動脈疾患に対するOMTの確立は,安定した冠動脈疾患においては場合により外科的治療や血管内治療の代替えとされるまでに発展した。しかし大変皮肉なことに,いったんOMTが確立した後は,多少の薬剤の変更はあっても,これにプラスして何か新しい治療法を加えようとした研究はことごとくnegative studyに終わったといってよい。そんな中,古くて新しい薬コルヒチンが今注目を集めている。
動脈硬化炎症説とコルヒチンの抗炎症作用
動脈硬化が炎症と深い関係があるとする動脈硬化炎症説は1976年にRossらが「傷害に対する反応」仮説を提出したことに始まる 1)2) 。当初は,血管内皮細胞の傷害とそれに引き続く血小板の活性化,血小板由来増殖因子による平滑筋の増殖が原因と考えられたが,その後,泡沫細胞がマクロファージに由来することや,種々の炎症細胞が動脈硬化巣に存在することから,1986年にマクロファージとサイトカインを中心とした傷害反応仮説に修正され,現在の動脈硬化炎症説の基礎となった 3)4) 。この総説は動脈硬化炎症説を解説することが目的ではないので深入りはしないが,近年は自然免疫の障害説なども提出され議論が続いているものの,結局決定的なメカニズムの解明には至っていない。

コルヒチンはイヌサフラン科のイヌサフラン(Colchicum autumnale)の種子や球根に含まれるアルカロイドで,長く痛風の薬として使用されてきた。主な作用として,細胞内微小管(microtubule)の形成阻害,細胞分裂の阻害のほかに,好中球の活動を強力に阻害することによる抗炎症作用が挙げられる。ところが皮肉なことに,ここにコルヒチンが動脈硬化の進展予防に何らかの作用を持つと考えられなかった理由がある。というのは,動脈硬化炎症説を考える人たちは単球やマクロファージ,免疫系細胞,それらによって産生される種々のサイトカインには注目するが,好中球には関心を示さなかったからだ。ちなみに好中球,多核球に対してこれだけ強力な抑制作用を持つ薬剤は,現在コルヒチン以外に知られていない。結局,今世紀に至るまでコルヒチンが動脈硬化性疾患の進展予防に何らかの効果を持つとは誰も考えなかったのである。
しかし突破口は意外な方面から開かれた。ニューヨーク大学のリウマチ研究室のCrittendenらが奇妙な事実に気付き報告したのだ。痛風患者に対してコルヒチンを使用していると心筋梗塞の有病率が低いというのである 5) 。
冠動脈疾患の二次予防とは直接関係しないが,コルヒチンが心膜炎に対する予防効果があるとする研究が2014年にImazioらのグループによって立て続けに発表されたことは,心臓領域であまり顧みられることのなかったコルヒチンに別の立場から光をあてた,いわば側面バックアップになったともいえる 6)7) 。これらが多くの研究者たちにとって意外だったのは,コルヒチンは痛風予防投与としても,発作が予感されるかなりの初期でないと効き目が少ないのが特徴であり,痛風発作以外への鎮痛・消炎作用はほとんど認められないと考えられていたからだ。コルヒチンは痛風発作の初期および家族性地中海熱に対しては標準薬として使用されていた 8) 。そのほか適応外としてアミロイドーシス,強皮症,ベーチェット病などに稀に応用されることがあったが,これらの報告以後は心膜炎についても適応が検討されるようになった。基礎研究が臨床上の発見に追随していないのが現状であるが,古薬コルヒチンの抗炎症作用のメカニズムについて改めて検討される可能性が高いのではないかと考えられる。