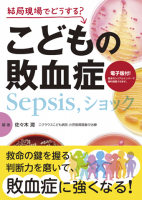お知らせ
ウィルムス腫瘍(腎芽腫)[私の治療]
ウィルムス腫瘍は,小児悪性固形腫瘍で神経芽腫についで頻度が高い腎原発悪性腫瘍であり,小児腎原発悪性腫瘍の80%を占める。およそ1万人に1人の割合で発症し,わが国では年間100例弱が発生すると推察されている。好発年齢は5歳未満で,特に3歳前に約半数が発症するとされる1)。
ウィルムス腫瘍は胎児性腫瘍のひとつで,胎生期の後腎芽組織から発生すると考えられており,腎芽腫とも呼ばれる。11p13 にあるがん抑制遺伝子WT1の異常がおよそ20%程度にみられると言われているほか,WT2,WTXやCTNNB1などの遺伝子関与も疑われている。
かつては腎芽腫に加え,腎ラブドイド腫瘍(RTK)や腎明細胞肉腫(CCSK)もウィルムス腫瘍に含まれていたが,近年はそれぞれ独立した腫瘍とされており,本稿では腎芽腫について述べる。
▶診断のポイント
腹部腫瘤,腹部膨隆を主訴に来院することが多い。

WT1や11p15.5に異常のある多発奇形症候群(WT1:W AGR症候群,Denys-Drash症候群,Frasier症候群など。11p15.5:Beckwith-Wiedemann症候群など)はWilms tumor predisposition syndromesと呼ばれ,ウィルムス腫瘍の発症リスクが高く,両側または異時性に多発することもあるため,注意が必要である。上記以外にも,Fanconi貧血やいくつかの過成長症候群(Perlman症候群,Simpson-Golabi-Behmel症候群など),または非過成長症候群(孤立性無虹彩症,Bloom症候群など)などが報告されている1)2)。
血液検査では特異的腫瘍マーカーがなく,単純X線写真でも神経芽腫や奇形腫でみられる石灰化像などの特徴的所見は稀である。腹部超音波検査で,腎原発の充実性のエコー像を認める。胸部を含む造影CTにより,腫瘍の進展や大血管との関係,腫瘍塞栓の有無,転移性病変の有無などから術前病期を診断する。
血液検査や画像検査では,他の腎原発悪性腫瘍との鑑別が困難なため,確定診断は摘出標本の病理診断による。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
わが国ではJWiTS(Japan Wilms Tumor Study Group)が中心となって,治療成績の向上に寄与してきた。標準的治療戦略としては,米国NWTS(National Wilms Tumor Study)プロトコルと同様,最初に画像検査をもとに腫瘍の進展範囲を判断した上で,手術による腫瘍摘出(患側の腎臓・腫瘍を完全摘出)を先行させ,正確な病期分類と病理組織診断を行ってから,これをもとに化学療法・放射線療法を組み立てる。
隣接臓器浸潤がある症例,肝静脈より頭側まで下大静脈への腫瘍栓が伸びていて一期的切除が困難な症例では,腫瘍生検による病理診断を行った後に化学療法を行って腫瘍の縮小を図り,二期的切除手術を行う。両側例では,左右それぞれで病期診断を行い,進行側に合わせた術前化学療法とそれに続く腎温存腫瘍摘出術を行う。
【病理診断】
本症の病理診断では,RTKやCCSKといった他の腎原発腫瘍を除外し,予後不良因子である退形成性(anaplasia)を有するかどうか,退形成性が限局性(focal anaplasia:FA)かびまん性(diffuse anaplasia:DA)かを確認することが臨床上重要である。退形成性がないものをfavorable histology(FH),あるものをunfavorable histology(UH)とし,UHの中でもDAはさらに予後が悪い。

残り1,540文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する