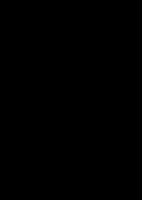お知らせ
■NEWS 【米国糖尿病学会(ADA)】GIP/GLP-1受容体アゴニストの腎保護作用をインスリンと比較:RCT“SURPASS-4”追加解析
2019年以来のライブ開催となる米国糖尿病学会(ADA)学術集会が、6月3日から米国ニューオーリンズで開催されている。その初日、GIP/GLP-1受容体アゴニストであるチルゼパチド(tirzepatide)をインスリン・グラルギンと比較した“SURPASS-4”試験の腎転帰が、Hiddo J.L.Heerspink氏(フローニンゲン大学メディカルセンター、オランダ)により報告された。
SURPASS-4試験は、心血管系(CV)高リスク2型糖尿病(DM)例に対する、チルゼパチドとインスリン・グラルギンのCVイベント抑制作用を比較した、ランダム化試験である。昨年報告された主解析において、チルゼパチドはインスリンに比べ、HbA1c(1次評価項目)をおよそ1~1.5%低下、体重も約10kg低下させたものの(いずれも有意)、「CV死亡・心筋梗塞・不安定狭心症入院・脳卒中」のハザード比(HR)は0.74も、95%信頼区間(CI)は「0.51-1.08」と有意差に至らなかった(非劣性は証明)。

今回報告されたのは、事前設定されていた「腎転帰」への影響である。
SURPASS-4の対象は、メトホルミン、SU剤、SGLT2阻害薬で管理不良(HbA1c:7.5-10.5%)、かつ「BMI≧25kg/m2」のCV高リスク2型DM 1995例である。平均年齢は64歳、男性が6割強を占めた。
推算糸球体濾過率(eGFR)平均は81mL/分/1.73m2。「eGFR<60mL/分/1.73m2」が18%、微量アルブミン尿陽性は28%、顕性蛋白尿を8%に認めた。
治療薬としては81%がレニン・アンジオテンシン系抑制薬、25%がSGLT2阻害薬を服用していた。
これらは3用量のチルゼパチド群と、インスリン・グラルギン群の4群にランダム化され、非盲検下で最長104週間、観察された。インスリンは就寝前10IU/日から開始し、空腹時血糖「<100mg/dL」となるよう調節が指示された。
その結果、チルゼパチド群における「顕性蛋白尿出現・40%以上のeGFR低下・末期腎不全・腎死」のHRは0.58(95%CI:0.43-0.80)と、インスリン・グラルギン群に比べ有意に低値となっていた。ただし内訳を見ると、「腎死」は両群とも発生せず、「末期腎不全」もインスリン・グラルギン群の0.5%のみ。「eGFR低下」はチルゼパチド群でHR:0.87も、95%CIは「0.56-1.33」だった。つまり有意差を認めたのは「顕性蛋白尿出現」のみである(HR:0.41、95%CI:0.26-0.66)。
そこで尿中アルブミンの推移を見ると、チルゼパチド群では治療開始42週間後に約20%低下するも、52週間後には上昇。開始時からの低下率は5%前後となる。そしてそれ以降はそのまま推移し、試験終了時の低下率は4.4%だった。一方、インスリン・グラルギン群では一貫して経時的な上昇を認め、最終的には試験開始時から56.7%の高値となっていた。
興味深いのはeGFRの推移である。インスリン・グラルギン群では一貫して低下が続いたのに対し、チルゼパチド群では開始時の81.8mL/分/1.73m2から、12週間後には約78mL/分/1.73m2まで低下するものの、その12週間後にはおよそ80mL/分/1.73m2にまで回復し(この時点でインスリン・グラルギン群と同等)、以降の低下率はインスリン・グラルギン群よりも若干だが抑制されていた(104週間後には2.0mL/分/1.73m2の有意高値)。
このSGLT2阻害薬にも似たeGFRの推移をもたらす機序としてHeerspink氏は、GLP-1刺激作用によるNHE3阻害作用を介した「尿細管糸球体フィードバック機構正常化」の可能性を指摘した。
またチルゼパチド群における尿中アルブミン低下作用について同氏は、GLP-1刺激作用による内皮機能改善を機序の1つとして挙げたが、別の研究者は、これまでのGLP-1アゴニスト臨床試験ではここまでのアルブミン尿抑制作用は認めなかったとした上で、GIP受容体刺激が関与している可能性を指摘した。
なお本報告では、両群の血圧推移は示されなかった。
本試験はEli Lilly and Companyから資金提供を受けて実施された。