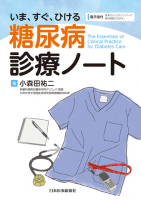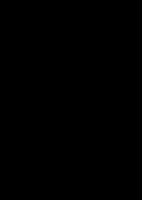お知らせ
骨粗鬆症(原発性)[私の治療]

骨密度の低下などによって脆弱性骨折のリスクが高まった状態で,閉経や加齢等によって発症する原発性と,薬剤の使用や骨密度低下をきたす疾患への罹患等によって発症する続発性とにわけられる。

▶診断のポイント
骨密度低下(若年成人平均値の70%以下または-2.5SD以下),脆弱性骨折(大腿骨近位部または椎体)の既往,大腿骨近位部や椎体以外の脆弱性骨折があり骨量減少(骨密度が若年成人平均値の80%未満)の場合に診断される。また,投薬基準としては,これらに加えて,骨密度が若年成人平均値の70%より大きく80%未満の場合には骨折評価ツール(FRAXⓇ)の10年間の骨折確率(主要骨折)15%以上か大腿骨近位部骨折の家族歴が挙げられる。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
目安とするのは年齢や既存骨折の有無およびその部位・個数などで,これらを組み合わせて大まかに重症度を軽症(65歳未満など比較的若年,および/または脆弱性骨折の既往なし,および/または骨密度が-3.3SD以上-2.5SD以下など),中等症(軽症と重症の間),重症(骨密度が若年成人平均値の70%以下,または-2.5SD以下でかつ1または2個以上の椎体骨折,または腰椎骨密度が-3.3SD未満,または大腿骨近位部骨折,またはSQ3の椎体骨折,または直近1カ月以内の脆弱性骨折)にわける。その上で,個々の状況や合併症の有無,治療歴の有無や使用薬剤,経済状況などを考慮して治療方針を立てる。
治療薬としては,大きく骨形成促進薬と骨吸収抑制薬にわけられるが,骨折の危険性の高い骨粗鬆症と判断される症例では,近年では経済状況が許せば積極的に骨形成促進薬を投与し,その後骨吸収抑制薬につなぐ逐次療法が骨量増加・骨折予防の点で効果が高い。