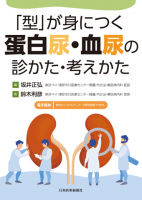お知らせ
特発性膜性腎症[私の治療]

特発性膜性腎症は,成人のネフローゼ症候群をきたす主要な疾患であり,病理組織学的に糸球体基底膜上皮下への免疫複合体沈着を特徴とする。悪性腫瘍・自己免疫性疾患・薬剤などを原因とする二次性膜性腎症に対して,明らかな原因がないものを特発性膜性腎症としていたが,近年はM型phospholipase A2 receptor(PLA2R)をはじめとする原因抗原が複数同定されている。
▶診断のポイント
【症状】
身体所見では圧痕性浮腫が最も主要な症状であり,胸腹水をきたすこともある。これに先立ち,蛋白尿に伴う尿の泡立ちを自覚する場合もある。また,発症時に血圧上昇を呈する頻度も高い。加えて,特発性膜性腎症では血栓症の合併頻度が高く,下肢浮腫の左右差や,圧痛・発赤・熱感がある場合には下肢深部静脈血栓症の合併を疑う。

【検査所見】
大量蛋白尿(尿蛋白≧3.5g/日またはg/gCr)とともに低アルブミン血症(血清アルブミン≦3.0g/dL)を呈し,ネフローゼ症候群の状態となることが多い。IgGとトランスフェリンのクリアランス比である尿蛋白の選択指数(selectivity index)は低選択性(≧0.21)となることが多い。高LDL-C血症などの脂質異常症を呈する頻度が高い。
近年,原因となる自己抗体の測定が可能となり(保険適用外),特発性膜性腎症の中で最も頻度の高い(50〜70%程度)PLA2R関連膜性腎症では,血中抗PLA2R抗体が陽性となる。
腎生検による病理組織学的検査では,糸球体基底膜上皮下への免疫複合体沈着を反映して,PAM染色光顕所見で糸球体基底膜のスパイク形成,蛍光抗体法でIgGの糸球体係蹄に沿ったびまん性顆粒状沈着が認められる。IgGのサブクラスではIgG4が主体であることが多い。

残り1,146文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する