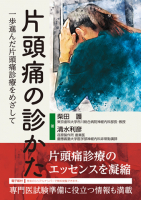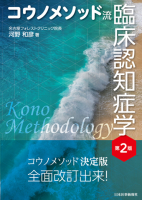お知らせ
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)[私の治療]

急性散在性脳脊髄炎(acute disseminated encephalomyelitis:ADEM)は代表的な中枢神経系の脱髄疾患のひとつであり,脳,脊髄,視神経に同時多発的な脱髄性病変を認めるが,詳細な病態機序は不明である。日本では人口10万人当たり0.4~1.0人の割合で発症するとされる。病因から大きく3つのグループ,すなわち感染性・ワクチン性・特発性にわかれる。小児に多いが,成人での発症もある。また単相性が多いが,中には再発するケースもある。発熱・頭痛・嘔吐などで発症し,同時ないし遅れて脱力・失調・脳神経麻痺・意識障害・痙攣など多彩な症状を呈することが多い。
▶診断のポイント
診断特異的マーカーはなく,診断には,経過・画像などから疾患を疑うことと,他疾患の十分な除外が重要である。最近は,myelin oligodendrocyte glycoprotein(MOG)抗体陽性のADEMの場合,MOG抗体関連疾患(MOG antibody-associated disease:MOGAD)と診断する傾向が強い。また,ADEMは多様な病態を含み,単一の疾患ではなく症候群とも考えられ,現在ADEMと診断されていても,今後新たな疾患として分類される可能性もある。

診断基準は,成人には広く使用されているものはなく,小児のみInternational Pediatric Multiple Sclerosis Study Group(IPMSSG)から2007年に暫定的な疾患定義が提案され,その後,2012年に改訂されている1)。
ADEMは典型的には単相性の経過をとるが,その症状や画像所見は発症から3カ月間は変動や増悪をしうる。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
ADEMと診断した場合には,早めに急性期治療を行う。具体的には,ステロイドパルス療法が基本であるが効果がなければ,血漿浄化療法や免疫グロブリン大量静注療法(intravenous immunoglobulin:IVIg)を検討する。コハク酸アレルギーなどでメチルプレドニゾロンなどが使えない場合も,血漿浄化療法やIVIgを検討する。初発の場合,再発予防治療は基本的に不要である。再発した場合には,再発予防薬を検討する前に,診断の見直しを十分行う。

残り1,070文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する