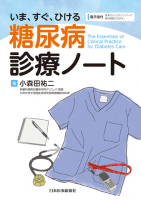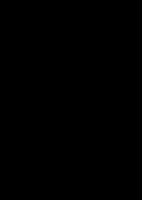お知らせ
■NEWS 【国際脳卒中学会(ISC)】2型DM例における再還流療法非実施の脳梗塞にGLP-1-RA追加で脳卒中減少。機能転帰改善も:中国RCT"LAMP"
血糖管理不良の脳梗塞例では、血栓溶解薬静注が見送られるケースもある[静注血栓溶解(rt-PA)療法適正治療指針 第三版]。そのような場合、GLP-1-RAを追加すると、脳卒中再発抑制と機能転帰改善を図れるかもしれない。中国で実施されたランダム化比較試験(RCT)"LAMP"の結果、明らかになった。2月5日からロサンゼルス(米国)で開催された国際脳卒中学会(ISC)にて、曁南大学(中国)のHui-Li Zhu氏が報告した。
【対象】
LAMP試験の対象は中国在住の、軽症脳梗塞(NIHSS≦3)か高リスクTIA(ABCD2≧4)発症から24時間以内で、血栓溶解/血栓回収療法を実施していない2型糖尿病(DM)636例である。脳卒中再発例も登録可能だったが「mRS≦1」例に限られた。心原性脳塞栓症は除外されている。27施設から登録された。

なおZhu氏によると、636例という数は当初の想定患者数には及んでいないという(登録遅延のため早期打ち切り)。
【方法】
これら636例は「標準」治療群と、標準治療にGLP-1-RA(リラグルチド)を追加する「GLP-1-RA追加」群にランダム化され、非盲検下で観察された。リラグルチドはランダム化初日から1日1回皮下注を90日間継続した(0.6~1.8mg/日)。
【患者背景】
年齢中央値は63.5歳、女性が36%を占めた。またHbA1cは8.2%だった(おそらく中央値)。
脳血管障害の内訳は脳梗塞が97%を占め、NIHSS中央値は2だった。類型としてはアテローム動脈硬化性が最多で50%近くを占め、次いで小血管閉塞(45%強)だった。TIA例(3%)のABCD2スコア中央値は4~5である。
【結果】
1次評価項目である90日間の「脳梗塞・脳出血」発生リスクは、「GLP-1-RA追加」群で有意に低かった(ハザード比[HR]:0.56、95%CI:0.34-0.91)。発生率は「7.9 vs. 13.8%」である(要治療数[NNT]は「17」)。両群のカプランマイヤー曲線は試験開始直後から乖離を始めたが、およそ30日が経過すると差はさほど広がらず、また発生率曲線もほぼ水平のまま推移した。
なお「脳梗塞」と「脳出血」に分けて解析すると、「GLP-1-RA追加」群における「脳出血」減少は有意とならず、傾向にとどまった(「脳梗塞」では有意差)。
2次評価項目の1つである90日後「mRS≦1」例の割合も、「GLP-1-RA追加」群で有意に多かった(87.3 vs. 77.8%。NNT「11」)。「mRS≦2」で比較しても同様だった。一方、「症候性頭蓋内出血」発生率は「GLP-1-RA追加」群が0.3%、「標準治療」群が0.6%だった(P=0.5)。「死亡」も順に0.3%と1.3%で有意差はなかった(P=0.1)。
本試験は登録患者数が当初予定に達していない(検出力不足)ため、 本試験で示唆されたGLP-1-RAの有用性は別試験であらためて検証する必要があると、Zhu氏は結語で述べた。
本試験は、広州科学技術プログラムから資金提供を受けて実施された。