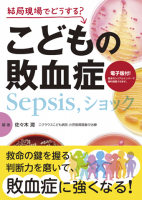お知らせ
熱性けいれん診療ガイドライン2015 【5分以上持続する痙攣発作にはジアゼパムまたはミダゾラムの静注を】
わが国における熱性痙攣の定義は,主に生後6~60カ月までの乳幼児に起こる,通常は38℃以上の発熱に伴う発作性疾患(痙攣性,非痙攣性を含む)で,髄膜炎などの中枢神経感染症,代謝異常,そのほかの明らかな発作の原因がみられないもので,てんかんの既往のあるものは除外する,とされている。
熱性痙攣は小児でよくみられる疾患のひとつであり,小児科医以外でも遭遇する機会が多い。そこで,『熱性けいれん診療ガイドライン2015』(文献1)から初期対応と検査のポイントについて紹介する。
(1)初期対応
痙攣が止まっている場合はルーチンにジアゼパム坐薬を使用する必要はない。痙攣発作が5分以上持続している場合はジアゼパムまたはミダゾラムの静注を行うか,静注可能な施設に搬送する。
(2)検査
ルーチンな検査は不要であるが,全身状態不良などにより重症感染症を疑う,痙攣後の意識障害が遷延する,脱水を疑う所見がある場合には血液検査が,髄膜刺激症状,30分以上の意識障害,大泉門膨隆などの細菌性髄膜炎をはじめとする中枢神経感染症を疑う所見がある場合には髄液検査が,脳炎・脳症を疑う所見がある場合には脳波検査が,発達の遅れを認める,発作後の麻痺を認める,焦点性発作や遷延性発作(持続時間15分間以上)がある場合には頭部画像検査が勧められる。
【文献】
1) 熱性けいれん診療ガイドライン策定委員会, 編:熱性けいれん診療ガイドライン2015. 日本小児神経学会, 監. 診断と治療社, 2015.