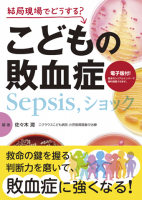お知らせ
小児へのフルワクチン接種で入院防止効果 【けいゆう病院・菅谷氏ら】
けいゆう病院など21病院が参加するグループが、小児を対象とした大規模研究で、インフルエンザワクチン接種によって入院防止効果が得られることを確認した。欧州疾病予防管理センター(ECDC)の学術誌『Eurosurveillance』(10月20日付)に論文が掲載された。同グループは昨年にも小児における入院防止効果を確認しており、2年連続でインフルエンザワクチンの入院防止効果が実証されたのは世界初。
同グループは、2014年11月~15年3月に受診し迅速診断を受けた生後6月~15歳の小児3752人を対象に、三価不活化ワクチンの有効性をテストネガティブ法(用語解説)によって評価。その結果、ワクチンによる発病防止効果は、全体では38%、14/15シーズンの流行株だったA香港型(H3N2)では37%だった。また、迅速診断で陽性だった者のうち入院した患者数をみると、ワクチン未接種者では236人だったのに対し、ワクチン接種者では106人と、55%の入院防止効果が確認された。
研究代表者の菅谷憲夫氏(けいゆう病院)は「ワクチンの評価手法の世界標準であるテストネガティブ法によって有効性が証明された意義は大きい。ワクチンへの不信感がくすぶっているが、実際には入院防止効果まであるので、小児への接種はぜひやるべきだ」と強調している。
ただし研究では、生後6~11月と13~15歳でのワクチンの有効性が認められなかった。菅谷氏は「乳児は抗体反応が弱いため、積極的に接種を勧めることはできない」と話している。13~15歳については「理由は分からないが、別の施設の研究でも同様の結果が出ている。中学生になるとワクチンの効果が落ちることを念頭に置くべきだろう」としている。 ![]()
テストネガティブ法:症例・対照研究デザインの1つ。ワクチン評価に関する研究では、診断で陽性だった者を「症例」、陰性だった者を「対照(test-negative control)」として、接種歴と効果の関係を後方視的に評価する。米英などの公衆衛生当局では、インフルエンザワクチンの標準的な評価法とされている。