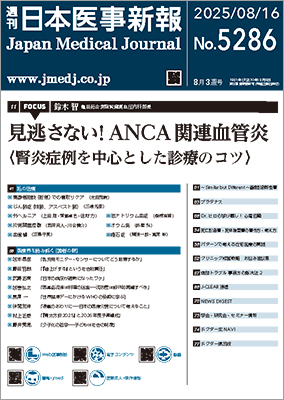お知らせ
(2)分子標的薬による心毒性への対応─血管新生阻害薬を中心に [特集:がん化学療法中の心血管系副作用にどう対処するか]

分子標的薬における血管新生阻害薬は幅広いがん種の治療に用いられ,中でも血管内皮増殖因子(VEGF)経路阻害薬が主体となっている。VEGF経路阻害薬はVEGFモノクローナル抗体とVEGF受容体に作用する小分子チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)の2つに大別される
分子標的薬の有害事象には,on-target toxicity(標的毒性)とoff-target toxicity(標的外毒性)の2種類の発症機序がある。VEGF経路阻害薬においても,VEGF経路に特異的な有害事象以外にVEGF経路阻害とは関連が低いとされるoff-target toxicityによる有害事象がある

VEGF経路阻害薬による心血管系有害事象は,主にVEGFによる心血管ホメオスタシス作用が障害されることで生じると考えられている
VEGF経路阻害薬により,高血圧,心不全・左室機能低下,冠動脈疾患,血栓塞栓症,蛋白尿・腎機能低下,QT延長などの心血管系有害事象が生じる
VEGF経路阻害薬による高血圧合併は,最も頻度が高い。この血圧上昇は,抗腫瘍効果のサロゲートマーカーとしても考えられている
VEGF経路阻害薬による心血管系有害事象は可逆的障害であることが多いとされるが,非可逆的障害となることもあり,注意深い評価,管理が求められる
1. がん分子標的薬
がん分子標的薬は,がん特異的に発現した蛋白質や特異的な細胞内シグナル分子を標的として抗腫瘍効果を発揮する薬剤である。がん細胞関連の特異的分子に対して作用するように設計あるいは選択され,開発されたものであり,基本的には正常細胞への影響が少なくなるよう設計された薬剤となっている。しかし実際には,その標的分子は必ずしもがん細胞特異的ではなく,正常細胞にも存在しており,各種有害事象が生じてしまうのも事実である。
分子標的薬は,製剤的分類として,(Ⅰ)受容体などの細胞外ドメインを標的とする高分子化合物である抗体薬,(Ⅱ)細胞内のシグナル伝達経路などを標的とする小分子化合物であるキナーゼ阻害薬,に大別される。
作用機序からは,①シグナル伝達阻害,②血管新生阻害,③細胞周期調節,の大きく3つに分類される。
①については,がん細胞に高発現しているシグナル伝達系に作用することで薬剤が抗腫瘍効果を示す。特に細胞の分化,増殖に深く関わるチロシンキナーゼに対する阻害薬が中心となっている。
②の血管新生阻害薬では,血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)を標的とするモノクローナル抗体をはじめ,VEGF受容体に作用するチロシンキナーゼ阻害薬(tyrosine kinase inhibitor:TKI)が主体となる。多数の標的を持つマルチキナーゼ阻害薬の多くは,VEGF経路阻害作用を含む。それ以外にテムシロリムスなどのmTOR阻害薬(mammalian target of rapamycine inhibitors)やサリドマイド系薬剤も血管新生阻害に関連する薬剤となっている。
③については,がん細胞の増殖に関わる細胞周期を阻害することで効果を発揮するが,CD20やプロテアソームを標的とした薬剤などがある。
本稿では,心血管系有害事象と関わりが深い血管新生阻害に関連した分子標的薬について概説する。

残り9,338文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する