お知らせ
(15) 精神・心身医学[特集:臨床医学の展望]

■精神・心身医学の現況と課題
2013年12月にG8認知症サミットがロンドンで開催されたのを受けて,2014年11月には「新しいケアと予防のモデル」をテーマとして認知症後継サミットが東京で開催された。わが国における認知症の社会的コストは現在試算中であるが,認知症が世界全体に与える社会経済的損失は計りしれない。認知症への国家レベル,地球レベルでの研究の推進,対策の強化が喫緊の課題となっている。
認知症に対する予防戦略のひとつとして,睡眠の問題がクローズアップされている。良質な睡眠がとれないと脳内にアミロイドベータ蛋白(amyloid beta protein:Aβ)が蓄積するようになり,逆にいったんAβが蓄積しはじめると不眠の増悪や睡眠パターンの変化が生じてくる。睡眠障害がアルツハイマー病(Alzheimer’s disease:AD)の病理と関連することはほぼ確実であり,睡眠のヘルスケアがADの発症や進展予防ともつながってくる可能性がある。
うつ病や自殺を未然に防ぐことも重要である。2014年6月に労働安全衛生法の一部が改正され,勤労者のメンタルヘルス対策の充実・強化などを目的として,従業員数50人以上のすべての事業場にストレスチェックの実施を義務づける法案が成立した。2015年度から実際にチェックが実施となるが,メンタルヘルス不全者への対応など難しい問題を抱えている。自殺に関しては,救急で救命された自殺未遂者への一定の介入・フォローアップが自殺企図の再発予防効果を持つという知見が日本から発信された。
統合失調症に関しても,精神病発症危険状態(at risk mental state:ARMS)の段階での対応の重要性が認識されてきているが,これらの問題を中心とした第9回国際早期精神病学会が2014年11月に東京で開催された。なお,10月には第3回日本ポジティブサイコロジー医学会も東京で開催されており,メンタルヘルスのテーマは全体として「疾患予防」から「健康で活発な生活の増進」へとさらにシフトしてきている。
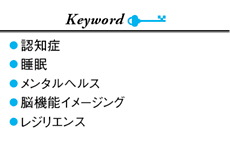
TOPIC 1
心の働きの脳機能イメージング
(1)「嘘と真実」の脳機能イメージング
2014年は虚言ないしは虚言と思われる言動が日本を騒がせた年であった。音楽家が,政治家が,そして科学者が,それぞれの分野で自らの輝かしい業績を主張し,彼らの言葉の真偽をめぐる議論は硬軟様々な話題を社会に提供してきた。
嘘を見抜くことは人類の普遍的とも言える大きな関心事である。嘘と真実を区別する技術としては,嘘に伴う情動の変化を自律神経の反応として測定するポリグラフがよく知られているが,現代では機能的MRI,脳波,光トポグラフィなどのニューロイメージングを用いて虚言そのものの脳内過程をとらえようとする手法が登場している1)。とはいえ,この領域の論文は多数発表されているものの,実用性に関しては,証言の真偽について機能的MRIで被告人の脳を検査した「証拠」が米国の裁判所に却下される事態が繰り返されているのが現状である。虚言が主観と一体化した脳内過程である以上,その神経基盤の同定はまだ遠い未来か,決して届かない領域にさえ見える。しかし,今年を振り返ってみても,科学の射程外にあると思われていた主観的な精神機能が,次々に解明に向かっている。
(2)「心の痛み」の脳機能イメージング
他者が身体の痛みを感じている場面を見ると,観察者の脳内の痛みに関連する部位が活動することはすでに機能的脳画像で示されている。「他人の痛みを感じる」ことは単なる比喩ではない。「痛み」に関する研究は近年では,社会の中で人々から拒絶された時に感じる苦痛のような,対人関係の中で生じる痛みの分析にまで発展している。そして痛みの対極にある報酬と合わせ,対人関係場面での社会的な情動が,身体的な快・不快と脳内過程を共有することを示す研究が続々と発表されている2)。
こうした知見については,進化的見地からは当然であるという冷めた見方もあろうが,精神医学的には,対人関係の中で生じる痛みの研究が疾患に関する理解を大きく進める可能性もある。たとえば,幼少期の外傷体験が成人の精神疾患とどのように関連するかはフロイト以来精神医学で綿々と続いているテーマであるが,実証的な研究の蓄積が続けられた結果,注意欠如・多動性障害(attention deficit/hyperactivity disorder:ADHD)の前頭葉に認められる所見が,幼少時の生育環境と関連することが示されるなど,精神科臨床の知と脳に関する所見とが様々なレベルで統合されつつある3)。
(3)疾患と性格的偏りとの境界
他人の痛みを知ることは共感性(sympathy, empathy)の起源であるが,最近では共感性とまとめられている機能をさらに細かく分節して扱うことも提案されている。精神機能を対応する脳基盤に基づいて分節していくことは精神現象の見方を精緻化させるものであるが,心の機能を脳機能に照らして理解するという流れの結果,疾患と性格的な偏りとの境界がますますあいまいになってきている。2013年に発刊された米国精神医学会の診断基準(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition:DSM-5)の日本語版『精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版』が2014年に出版されたが,この中で従来パーソナリティ障害を包含していたⅡ軸が廃止され,統合失調症や双極性障害などの疾患概念を包含するⅠ軸の中に包含されることになったのは,歴史の必然と言えるかもしれない。
このような潮流,すなわち伝統的には疾患とは一線を画するとされていたパーソナリティ障害を精神科の対象として取り込むのは,医療化ないしはdisease-mongeringであるという批判は免れないかもしれない。一方で,このような方向性は,従来は実質的に有効な治療法に乏しかったパーソナリティ障害を,より洗練された技法(薬物療法,精神療法を問わず)で治療していく端緒となるかもしれない。
認知機能という語でとらえられるものを,人間のあらゆる心の機能に拡大していくことは,もはや誰にも止めることのできない潮流である。この潮流が精神医学の診断と治療をより科学的なものにすることは確かである。しかし,性格の偏りと疾患の境界とを溶解させることは,あるいは共感という脳機能を解明することは,さらに人間の嘘をすべて暴くことは,はたして人を幸福に導く営みであろうか。ニューロサイエンスの知見を絶えず吸収する一方で,精神医学の役割を絶えず振り返って考えることが,臨床家にはますます求められるようになっていると言えよう。
【文献】
1) Farah J, et al:Nat Rev Neurosci. 2014;15(2): 123-31.
2) Ruff CC, et al: Nat Rev Neurosci. 2014;15(8): 549-62.
3) McLaughlin KA, et al:Biol Psychiatry. 2014; 76(8):629-38.
(村松太郎 三村 將)

残り3,493文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する













































