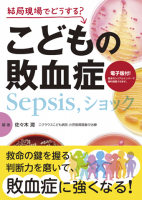お知らせ
【人】溝口史剛さん「いつか虐待で苦しむ子どもをゼロにしたい」

溝口史剛さん(Mizoguchi Fumitake)
米国の子ども虐待医学書を翻訳した医師

1975年神奈川県生まれ。99年群馬大卒。同大附属病院小児科などを経て、2010年より群馬県済生会前橋病院小児科部長。NPO法人子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク理事。日本子ども虐待医学研究会評議員。
いつか虐待で苦しむ子どもをゼロにしたい
米国小児科学会が2008年に発行した子ども虐待の医学書を日本子ども虐待医学研究会の有志とともに翻訳し、『子ども虐待医学』(明石書店)を出版した。870頁超の大著は、50年にわたる子ども虐待医学研究の集大成だ。
「日本のガラパゴスな議論を変えるには、欧米のエビデンスを紹介することが必要」。翻訳のきっかけはそんな問題意識だった。
日本で子ども虐待に光が当たり始めたのは1990年代に入ってからで、歴史が浅い。「米国では『子ども虐待医学』が小児科学のサブスペシャルティとして認められ、専門医も存在する。日本でもエビデンスに基づいた診断をするために本書を活用してほしい」
例えばこれまでにも、乳幼児の硬膜下血腫の虐待の可能性について様々な議論があった。最新の虐待医学では、『まれに、後方転倒で出血を起こすこともありうるが、その場合には予後良好であり、予後不良の硬膜下血腫は虐待の可能性がきわめて高い』と位置づけられている。「虐待を医学的に議論する上で、まだまだ感情的になったり、極論に走ることが起こっている。客観的で学究的な議論をする土壌を形成する必要を感じています」
□
溝口さんは小児内分泌の専門医でもあるが、多くの虐待事例を経験する中で、09年ごろから虐待医学に本腰を入れ始めた。
「虐待事例は、支援と介入の狭間で悩み、とても感情的に揺さぶられ、割くべき労力も大きく疲弊しやすい。その対応が個人の消耗的取組にとどまっていては、広がりが阻害される。虐待を早期発見し、子どもへのダメージを最小限にとどめるために、医師が通常の診療行為として行動できるシステムが必要です」
三層構造の医療機関間連携システムの構築、虐待事例対応時の診療報酬上の評価、虐待医学の専門性が医師のキャリアアップにつながる制度創設―。そうした体制の整備を目指す。
「現役の我々が頑張って、『子どもをより優先する社会』というバトンを次世代に渡したい。そのリレーがつながれば、何世代かかけて虐待で苦しむ子どもをゼロに近づけることは、決して夢物語ではないと信じています」

子どもから虐待被害事実を聞き取る米国の民間資格「司法面接士」の養成講師も務める。写真は2010年の資格認定の際の一枚