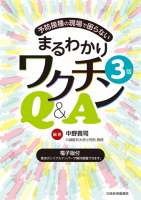お知らせ
マーモット元世界医師会長、日本は健康格差の縮小に「もっと関与を」―日医シンポジウム
日本医師会は16日、「国際社会と医療政策」をテーマにシンポジウムを開催した。サー・マイケル・マーモット元世界医師会(WMA)会長は「日本の医療分野での国際貢献度はまだ高いとは言えない」と指摘。気候変動や経済格差に伴い深刻化する健康格差の拡大に対し「日本も解決に協力する必要がある」と訴えた。
マーモット氏は討論の中で、健康の社会的決定要因に着目し、健康格差を縮小する政策を実現するためにも「医師は健康創造の牽引者として、公衆衛生と国際保健に関わることが望ましい」と語った。

座長を務めた渋谷健司氏(東大院教授)は「国際保健は一般臨床医からは遠い問題に聞こえる」と提起。これに対し、現WMA会長の横倉義武氏(日医会長)は「東日本大震災の被災地での医療救護活動では、海外の厳しい環境で活躍する医師に助けられた」と述べ、インフラ整備の不十分な環境下の医療で得た知見が、自国の災害医療の質を高めうるとの考えを示した。
國井修氏(世界エイズ・結核・マラリア対策基金局長)も「国際保健は教え合い。途上国から学べることは多い」と述べ、北朝鮮がマラリア感染大国であるとの例を示しつつ「公衆衛生上の脅威をグローバルに考えることは安全保障にもつながる」とした。
黒川清氏(日本医療政策機構代表理事)は、日本が先進7カ国(G7)の中で最も頻繁に「グローバルヘルス」をサミットで取り上げてきたことに触れ、「それこそがレガシー」と強調。感染症だけでなく高齢化や貧困への対応についても「世界中が日本を見ている」と述べた。
公衆衛生上の問題にグローバルな視点から関わる4人のシンポジストが討論