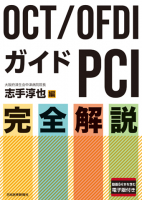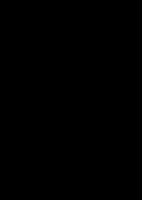お知らせ
学会レポート─2020年欧州糖尿病学会(EASD)[J-CLEAR通信(120)]

9月21日から5日間にわたり、欧州糖尿病学会(EASD)がオンライン開催された。最終日までに2万人を超える参加者があり、スライド発表264報、ポスター発表712報が報告された。参加者が最多だった国はブラジルで、日本はトップ10に入っていなかった。ここでは、話題の大規模試験関連情報と興味深い観察研究をご紹介したい。
TOPIC 1
VERTIS CV試験:論文未掲載最新データの報告も
6月の米国糖尿病学会で報告され(Web医事新報6月18日既報)、NEJM誌にも結果が掲載された1)VERTIS CV試験について、追加解析を含む成績がFrancesco Cosentino氏(カロリンスカ大学、スウェーデン)により報告された。

VERTIS CV試験の目的は、SGLT2阻害薬“ertugliflozin”による2型糖尿病(DM)例への「心血管系(CV)死亡・心筋梗塞・脳卒中」(3-point MACE)抑制作用が、プラセボに非劣性であることの証明にあった。
対象は、脳・心・末梢動脈のいずれかにアテローム動脈硬化性疾患を有する2型DM患者8246例である。1型DM、推算糸球体濾過率(eGFR)30mL/分/1.73m2未満、NYHA分類Ⅳ度心不全などは除外されている。
平均年齢は64歳、70%を男性が占めた。DM罹患期間は平均13年間、HbA1c平均値は8.2%。平均BMIは32kg/m2だった。報告後の総合討論では、この患者群がEMPA-REG OUTCOME試験2)に類似しているとの指摘があった。
これら8246例は、プラセボ群、低用量SGLT2阻害薬群、高用量SGLT2阻害薬群の3群にランダム化され、二重盲検法で平均3.5年間観察された。なお解析にあたっては、SGLT2阻害薬群は低・高用量2群を併合し、1群として解析された(この点もEMPA-REG OUTCOME試験と同様)。
その結果、1次評価項目である3-point MACEの、SGLT2阻害薬群における対プラセボ群ハザード比(HR)は0.97、95%信頼区間(CI)は0.85–1.11となり、非劣性は確認されたものの(P<0.001)、優越性の証明には至らなかった。SGLT2阻害薬による3-point MACE抑制作用がプラセボを上回らなかったのは、DECLARE-TIMI 58試験3)と同じである(HR:0.93、95%CI:0.84–1.03)。
一方、DECLARE-TIMI 58試験のもう1つの1次評価項目であり、同試験ではSGLT2阻害薬群における有意なリスク減少が認められた「CV死亡・心不全入院」(HR:0.83、0.73–0.95)だが、VERTIS CV試験では2次評価項目として検討されたものの、有意なリスク減少を認めなかった(HR:0.88、0.75–1.03)。しかし本学会で報告された、「心不全入院」の初発だけでなく再発まで含めた成績では、SGLT2阻害薬群において「CV死亡・心不全入院」リスクは有意に減少していた(発生率比:0.83、0.72–0.96)。
本試験は、Merck Sharp & Dohme(MSD)社とPfizer社からの資金提供を受けて実施された。またNEJM誌への投稿では、Merck社とPfizer社の資金により、Engage Scientific Solutions社の援助を受けた。
TOPIC 2
VERTIS CV試験:なぜ、有意差とならなかったのか。現地ディスカッション
VERTIS CV試験は、SGLT2阻害薬による2型DM例の「CV死亡・心不全初回入院」抑制作用がプラセボ群を上回らなかった初めての大規模ランダム化試験となった。なぜ他試験と結果が異なったのか—。本学会における議論を紹介したい。
総合討論ではまずDavid Z.I Cherney氏(トロント大学、カナダ)が、VERTIS CV試験参加例は他試験に比べ、潜在的に腎機能の良好な患者が多かった可能性を指摘した。心腎連関を考慮すれば、VERTIS CV試験ではその分CVリスクの低い集団を対象としていたことになり、そのためSGLT2阻害薬によるCV疾患抑制作用が現れにくかったのではないかとの推察である。
同氏が今回報告したVERTIS CV試験の腎転帰追加解析(事前設定)によれば、プラセボ群では当初およそ77 mL/分/1.73m2だったeGFRが、48カ月後も約74mL/分/1.73m2に保たれていた。一方、例えばEMPA-REG OUTCOME試験4)プラセボ群におけるeGFRは、当初の76mL/分/1.73m2から40カ月後、69mL/分/1.73m2まで低下していた。またDECLARE-TIMI 58試験プラセボ群のeGFRも、当初の85mL/分/1.73m2から48カ月後には10mL/分/1.73m2以上の低下幅を認めた。
Cherney氏による、この「VERTIS CV試験では対象が他試験に比べCV低リスクだったため、SGLT2阻害薬のCV保護作用を確認できなかった」との仮説との関連で、参考までにFrancesco Cosentino氏(カロリンスカ大学、スウェーデン)が報告した事前設定追加解析の結果を紹介したい。
それによれば、「心不全初回入院」での検討ではあるが、SGLT2阻害薬による抑制作用は、試験開始時eGFR「60 mL/分/1.73m2」「未満」で「以上」に比べ、有意に強くなっていた(交互作用P値=0.04)。同様に、利尿薬全般、あるいはループ利尿薬の、「使用(必要)」群では「非使用(不要)」群に比べ、SGLT2阻害薬による抑制作用が有意に強力だった(交互作用P値はそれぞれ0.02、0.01)。
一方、Bernard Charbonnel氏(ナント大学、フランス)は、人種構成の違いに言及した。すなわち、EMPA-REG OUTCOME試験では約2割を占めていたアジア人が、VERTIS CV試験では6%強のみだった。アジア人では他人種と比べ、SGLT2阻害薬によるCVイベント抑制作用の強い傾向が、EMPA-REG OUTCOME試験2)から報告されていた(ただし交互作用P値は>0.05)。
TOPIC 3
SGLT2阻害薬によるCVイベント抑制試験の最新メタ解析:減少するCVイベントは何か
本学会では、VERTIS CV試験を含む、SGLT2阻害薬による2型DM例のCVイベント抑制作用を検討したランダム化試験のメタ解析も、Darren K McGuire氏(テキサス大学、米国)により報告された。
同氏がメタ解析の対象としたのは、今回報告されたVERTIS CVに、EMPA-REG OUTCOME、CANVAS Program、DECLARE-TIMI 58、CREDENCEの4試験を加えた、5つのプラセボ対照ランダム化試験である。まず、「CV死亡・心筋梗塞・脳卒中」(3-point MACE)は、SGLT2阻害薬によりプラセボに比べ、有意なリスク低下が確認された(HR:0.90、95%CI:0.85–0.95)。試験間に存在するバラツキの指標であるI2は23.4%で「不均一性は大きくない」とMcGuire氏は評価した。ただし、この結果が当てはまるのは、アテローム性動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)を有する2型DM例のみのようである。ASCVD合併の有無で分けると、「ASCVDなし」ではプラセボとの有意差は認められなかった。
次いで「CV死亡」のみで検討すると、SGLT2阻害薬群全体におけるHRは0.85(95%CI:0.78–0.93)と有意低値だったものの、I2は64.3%という高値だった。このバラツキの大きさはEMPA-REG OUTCOME試験に由来するとMcGuire氏は指摘。同試験はSGLT2阻害薬群における「CV死亡」の有意なリスク減少が報告された唯一の試験であると同時に、リスク減少幅も他試験に比べ、格段に大きかった。
一方、「心不全初回入院」については、SGLT2阻害薬群における対プラセボ群HRは0.68(0.61–0.76)で、I2も0%という結果だった。
これらの結果を踏まえMcGuire氏は、心不全進展を抑制したければSGLT2阻害薬を優先するが、ASCVD予防を重視するならGLP-1アナログ製剤を選ぶ。この両剤はおそらく、(CVイベント抑制に関し)補完関係にあると、のちの討論で述べていた。
TOPIC 4
2型DMの成因により死亡リスクが異なる可能性:長期間観察研究
2型DMの成因としては、よく知られているように、「β細胞機能の低下に伴うインスリン分泌低下」と「インスリン抵抗性増大」がある。今回のEASDでは、同じ2型DMでも、成因により長期の死亡リスクが異なる可能性が示唆された。スウェーデンにおける前向き観察試験の結果である。Julia Otten氏(ウメオ大学、スウェーデン)が報告した。
解析対象となったのは、2型DMと診断された864例である。診断された年齢(中央値)はいずれも60歳、男性の占める割合はおよそ6割だった。
これらをOtten氏らは、観察開始時「HOMA-S>中央値」で「インスリン抵抗性弱」、「HOMA-β<中央値」ならば「β細胞機能低下」と定義し、4群に分けた。
その結果、「抵抗性・弱/β機能・減」(インスリン分泌低下DM)群が31.5%、「抵抗性・強/β機能・維持」(インスリン抵抗性増大DM)群も31.5%、「抵抗性・強/β機能・減」群は18.4%、「抵抗性・弱/β機能・維持」群が18.6%という分布となった。
その上で15年間(中央値)観察中の死亡リスクを比較したところ、「インスリン分泌低下DM」群に比べ、「インスリン抵抗性増大DM」群では、死亡HRが1.58(95%CI:1.06–2.36)と有意高値となっていた。性別や2型DM診断年齢、高血圧、総コレステロール、BMIなどを補正後の数字である。一方、癌死のリスクは、「インスリン分泌低下DM」群と「インスリン抵抗性増大DM」群の間に有意差は認めなかった。ただしCペプチド濃度高値に伴い、総死亡、癌死いずれのリスクとも有意に増加していた。
Otten氏はこの結果から、「2型DM診断時のインスリン抵抗性は死亡の独立したリスクだが、β細胞機能低下はそうではない」と結論していた。
TOPIC 5
DKD表現型別の心・腎転帰比較:単一施設10年超追跡
近年、糖尿病性腎臓病(DKD)という概念が提唱され、糖尿病性腎症には含まれない、アルブミン尿陰性の腎機能低下も、2型DM例の腎合併症として包括的に捉えるようになりつつある。このDKD、表現型により転帰が大きく異なる可能性が、Giuseppe Penno氏(ピサ大学、イタリア)により報告された。
同氏らが解析対象としたのは、自施設で登録した2型DM患者986例である。これらを以下の4群に分け、その後の転帰を比較した。すなわち、「アルブミン尿陰性(<30mg/g)」かつ「腎機能低下が軽度まで(eGFR≧60mL/分/1.73m2)」の「非CKD」群(79.0%)と、「腎機能低下が軽度まで」ながら「アルブミン尿陽性」の「ステージ1-2 DKD (1-2 DKD)」群(14.6%)、さらに「アルブミン尿陰性」ながら「腎機能中等度以上低下」の「アルブミン尿陰性(-Alb)DKD」群(3.4%)、アルブミン尿を認め、腎機能も中等度以上低下した「アルブミン尿陽性(+Alb)DKD」群(3.0%)─の4群である。
その結果(平均12.9年観察)、「末期腎不全」への移行リスク(諸因子補正後)が、「非CKD」群(4.38/1000例・年)に比べ有意に高かったのは、「+Alb DKD」群(35.7/1000例・年)だけだった(HR:5.37、95%CI:2.46−11.72)。
一方、重大CVイベントは、「非CKD」群(21.6/1000例・年)に比べ、有意なリスク増加(諸因子補正後)を認めたのは、「1-2 DKD」群(38.5/1000例・年)のみだった(平均11.3年観察)。
【文献】
1) Cannon CP, et al:N Engl J Med. 2020;383(15):1425-35.
2) Zinman B, et al:N Engl J Med. 2015;373(22):2117-28.
3) Wiviott SD, et al:N Engl J Med. 2019;380(4):347-57.
4) Wanner C, et al:N Engl J Med. 2016;375(4):323-34.