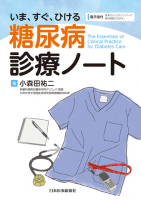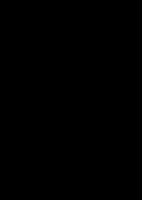お知らせ
■NEWS 【欧州糖尿病学会(EASD)】DPP-4阻害薬24週間服用は心不全合併2型糖尿病例の心臓に悪影響を及ぼさず:RCT“MEASURE-HF”

心血管系(CV)高リスク2型糖尿病(DM)例に対するDPP-4阻害薬は、ランダム化試験(RCT)“SAVOR-TIMI 53”において心不全(HF)入院が相対的に27%増加したため、心臓に対する安全性に懸念を感ずる向きもあった。しかしHF合併2型DM例をMRIで評価したところ、DPP-4阻害薬の少なくとも24週間服用では、心臓に対する影響はプラセボと同等だった。9月27日からオンライン開催された欧州糖尿病学会(EASD)において、RCT“MEASURE-HF”の結果として、Benjamin Scirica氏(ブリガム&ウィメンズ病院、米国)が報告した。なお、筆頭著者は心不全研究のレジェンド、Bertram Pitt氏である。
MEASURE-HF試験の対象は、HF標準治療を受けながらも「左室駆出率(EF)<45%」、かつ「NT-proBNP>300pg/mL」の2型DM 348例である。世界10カ国から登録され、アジア・太平洋地域からの参加例も13.8%含まれている。

平均年齢は約65歳、男性が7割弱を占めた。SGLT2阻害薬の服用率は約10%だった。
これら348例は、SAVOR-TIMI 53試験で用いられたDPP-4阻害薬であるサキサグリプチン群(112例)、対照としてシタグリプチン群(115例)とプラセボ群(121例)にランダム化され24週間、二重盲検法で観察された。
その結果、1次評価項目であるMRI評価「左室拡張末期容積係数(LVEDVi)」は、サキサグリプチン群で0.93mL/m2、シタグリプチン群も1.09mL/m2、プラセボ群で3.53mL/m2の増加を認めたが、群間に有意差はなかった(MRI評価は中央単一施設で実施)。
同様に、左室収縮末期容積係数とEFの変化にも、サキサグリプチン群とプラセボ群間に有意差はなかった。またNT-proBNPは両群とも、20pg/mL前後の有意な低下を認めた。
参考までにHF入院率だが、サキサグリプチン群6.3%、シタグリプチン群5.2%、プラセボ群5.8%という値だった(検定なし)。
本試験はAstraZenecaから資金提供を受けて実施された。