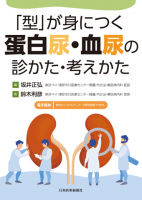お知らせ
尿細管性アシドーシス[私の治療]

尿細管性アシドーシスは,先天性や後天性の原因による腎臓尿細管機能異常により,尿中へのH+排泄,または,HCO3-の再吸収が障害され,酸血症を起こす病態の総称である。尿細管性アシドーシスを起こす原因疾患の鑑別が重要である。また,病態生理に応じた最適な治療法は各病型で異なるため,病型分類を含めた診断が重要である。
▶診断のポイント
アニオンギャップが正常の高Cl性代謝性アシドーシスで,薬物や腸管からのHCO3-の喪失などが除外されれば診断が確定される。尿中pHや尿アニオンギャップ,塩化アンモニウム負荷試験や重炭酸負荷試験によって病型診断は可能となるが,遺伝性を疑う症例においては遺伝子診断がより正確な確定診断となる。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
対症療法が中心となる。治療の基本は,アルカリ製剤投与による代謝性アシドーシスの補正である。また,病型に応じて低カリウム血症または高カリウム血症を起こすため,病型に合わせてカリウム値を是正する必要がある。特に,小児期においては成長障害などの是正が可能であり,早期の診断と治療介入が重要である。
さらに,原因疾患の鑑別を早期に進める。遺伝子異常に伴うもの以外にも,自己免疫疾患,カルシウムなどの電解質異常,薬剤など,様々な原因による二次性尿細管性アシドーシスも多くあり,二次性の場合には原疾患の治療も同時に,最優先で行われる必要がある。
尿細管性アシドーシスの診断がされれば,病型分類を行う。遺伝性の尿細管性アシドーシスは,原因遺伝子によって病態の本質が異なっており,主にⅠ/Ⅱ/Ⅳ型の3つの型がある。遠位尿細管でのH+分泌障害によるⅠ型,近位尿細管でのHCO3-の再吸収障害によるⅡ型,アルドステロン欠乏あるいは作用不全により遠位尿細管におけるK+とH+の排泄が障害されるⅣ型にわけられる。Ⅰ/Ⅱ型では低カリウム血症を呈するのに対して,Ⅳ型は高カリウム血症を起こす点に注意が必要である。
治療の基本は,アルカリ製剤投与によるアシドーシス補正である。その上で,血清カリウム値の是正を行う。I型においては,クエン酸投与によって尿中Ca溶解度を上げて腎結石予防ができるため,アルカリ製剤・クエン酸の配合剤を使用する。Ⅱ型においては,さらに多くのHCO3-が必要となる。また,ファンコーニ症候群を合併している場合は,骨軟化症を予防するため活性型ビタミンD製剤を投与する。Ⅳ型では,逆に高カリウム血症のためカリウム制限やイオン交換樹脂による治療が必要な場合が多く,低アルドステロン状態が明らかな場合は,体液貯留や血圧上昇に注意しつつミネラルコルチコイド製剤を用いることがある。偽性低アルドステロン症Ⅱ型の場合は,少量のサイアザイド製剤が著効する。

残り1,084文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する