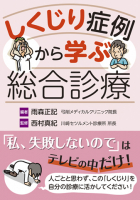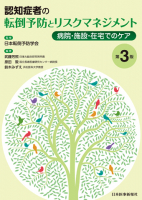お知らせ
在宅での死亡診断・死体検案[私の治療]
人間が必ずいずれ迎える死。超高齢多死社会においての現代の死亡場所は,病院78.4%,自宅12.4%,老人ホーム3.2%,診療所2.4%,介護老人保健施設1.1%,その他2.4%となっている(厚生労働省「人口動態調査」)。近年では,若干数であるが,病院死亡より自宅死亡が数字上増えているようにもみえるが,自宅死亡における死体検案(警察取り扱い死亡数に基づくものとして)の増加と突合すると,在宅医療の普及とともにいわゆる在宅看取りが増加しているとは決して言いきれない。
たとえば,在宅医療の患者が何らかの理由で主治医と連絡がつかず,自宅で孤立死・孤独死となったりする。また,主治医の指示による救急搬送や,施設からの救急搬送による検案事例も増加傾向にある。これらは在宅主治医,配置医あるいは嘱託医による24時間対応,在宅・施設看取りの問題にもつながる。
国は2024年度診療報酬改定においても,質の高い在宅医療提供(たとえば医療機関連携における24時間サポートシステムや,患者の人生の最終段階における医療・ケアに関する情報をICTを用いて共有し,指導・管理を行うこと)に対して加算評価をしており,主治医として最期まで責任をもって支えていくことが必須である。
▶死亡診断書と死体検案書の使いわけ
人口動態調査は,市区町村において各届書および死亡診断書等に基づいて調査票が作成され,保健所,都道府県で調査票の調査が行われ,厚生労働省で人口動態統計として取りまとめられている。正確な統計作成には調査票が正しく記載されることが前提であり,今後データ化されることにより死因状況なども明確になると考えられる。

医師は「診療管理下にある患者が,生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「死亡診断書」を,それ以外の場合は「死体検案書」を交付する。ただし,検案や死体検案書については監察医・警察医のみの交付とされている地域もある。
医師は,主治医でなくても同一医療機関内での情報共有がされている場合や,別の医療機関であっても担当医師から生前の診療情報の共有または提供を受けるなどして,死亡した患者の生前の心身の状況に関する情報を正確に把握できた場合に限り,生前に診療を担当していなかった医師でも死亡後に診断を行った上で,生前に診療を受けていた傷病に関連して死亡したと判断した場合には,死亡診断書の交付は可能である。このことは以前も,通例状況で同様の判断がされていたが,「令和6年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」1)に明記された。
なお,医師が患者の死亡に立ち会えなかった場合,死亡診断書を発行するためには,患者の死亡後改めて自ら診察を行う必要がある。
また,死体に異状があると認められた場合は,所轄警察署に届け出る必要がある(医師法第21条)。

残り953文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する