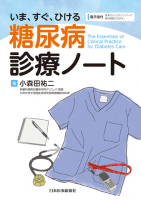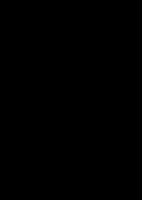お知らせ
■NEWS 【米国心臓病学会(ACC)】経口GLP-1RAでCV高リスク2型DM例のCVイベント抑制も、腎保護作用は観察されず:RCT“SOUL”

GLP-1受容体作動薬(GLP-1RA)は数多くのランダム化比較試験(RCT)で、高リスク2型糖尿病(DM)例に対する心腎保護作用が報告されている。しかしいずれも使われたのは注射剤だ。そのため、経口GLP-1RAの2型DM例臓器保護作用のエビデンスが待たれていた。
その待望のエビデンスが、3月29日から米国シカゴで開催された米国心臓病学会(ACC)学術集会で報告された。RCT"SOUL"である。心血管系(CV)イベントではプラセボに比べ有意差を認めたが、注射剤で報告されていた腎保護作用は確認されなかった。またSGLT2阻害薬との併用は、費用対効果も考慮する必要がありそうだ。

UTサウスウェスタン・メディカル・センター(米国)のDarren K. McGuire氏が報告した。
【対象】
SOUL試験の対象は、血管系疾患(冠動脈疾患、脳血管障害、症候性末梢動脈疾患、慢性腎臓病の少なくとも1つ)を合併している50歳以上の2型DM患者9650例である。日本を含む世界33カ国から登録された。
平均年齢は66歳、HbA1c平均値は8.0%、DM罹患期間は中央値で14.5年強という長きに及んでいた。にもかかわらず推算糸球体濾過率(eGFR)は比較的維持されており、平均で74mL/分/1.73m2だった。なお、欧米人が多数を占めたためか、体重は平均で88kg、BMI平均も31kg/m2という高値だった。
【方法】
これら9650例は全例、DM・CV疾患標準治療を実施の上、経口GLP-1RA(セマグルチド3~14mg/日)群とプラセボ群にランダム化され、1次評価項目である「CV死亡・心筋梗塞(MI)・脳卒中」が1225例で発生するまで二重盲検法で継続された。
【結果】
・1次評価項目
平均47.5カ月間観察後、経口GLP-1RA群における「CV死亡・MI・脳卒中」ハザード比(HR)はプラセボに比べ、0.86(95%CI:0.77-0.96)の有意低値となった。治療必要数(NNT)は「167/年」。McGuire氏によれば、3年間では「50」になるという。
内訳を見ると、「CV死亡」「MI」「脳卒中」のいずれも一貫して、経口GLP-1RA群で減少傾向を認めた。両群のカプランマイヤー曲線は開始後半年を待たずに乖離を始め、その差はおよそ36カ月後まで開き続けた(その後はほぼ平行)。
一貫していたのは、事前設定された各種サブグループ解析も同様である。「年齢」や「性別」「BMIの高低」「参加地域」「SGLT2阻害薬併用の有無」はいずれも、経口GLP-1RAによる「CV死亡・MI・脳卒中」抑制に有意な影響を与えていなかった。ただしSGLT2阻害薬「非併用」群(73.1%)では、経口GLP-1RAによる「CV死亡・MI・脳卒中」抑制NNTが「162/年」だったのに対し、「併用」群では「278/年」とかなり増えていた[同学会中公表Marx N, et al:Circより算出]。
・2次評価項目
一方、2次評価項目である「複合腎イベント」(心腎死亡・永続的なeGFR「<15」/「半減」・腎代替療法への移行)は、両群間に有意差を認めなかった。経口GLP-1RA群におけるHRは0.91(95%CI:0.80-1.05)、カプランマイヤー曲線も最後まで乖離に向けた傾向は見られなかった。本試験と同様、心腎高リスク2型DM例を対象に、同GLP-1RA注射剤を用いたRCT"FLOW"とは対照的な結果である(GLP-1RA群で腎症発症・増悪は相対的に36%のリスク減少)。
【考察】
質疑応答では注射剤との使い分けが取り上げられた。すなわち、同薬注射剤で腎保護作用が証明されている以上、そのような作用が認められなかった経口剤は注射剤忌避に対するオプションという位置付けであるべきか、という問いである。しかしこの点につきMcGuire氏から明確な回答は聞かれなかった。
本試験はNovo Nordiskから資金提供を受けて実施された。同社は試験マネージメントとデータ解析も担当した(解析は他統計会社が検証)。さらに原稿執筆・編集補助の費用も同社が負担した。また論文著者18名中6名は同社所属だった。本試験は報告と同時にNEJM誌ウェブサイトで公開された。