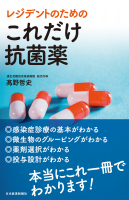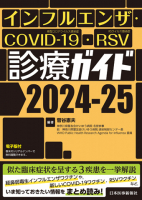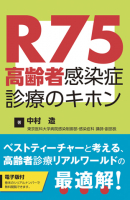お知らせ
梅毒[私の治療]

梅毒は,性感染症のひとつで,細菌である梅毒トレポネーマに感染して起こる。梅毒トレポネーマは性器や口などによる性行為や性的接触によって感染する。日本では感染症法の全数報告対象(5類感染症)であり,診断した医師は7日以内に最寄りの保健所に届け出ることとなっている。梅毒は2015年前後から急増し,2023年には2013年と比較して男性患者が10倍,女性患者は23倍になっている。年代別でみれば女性は20~30歳代が,男性は20~50歳代が多くを占めている。日本では,1948年から約20年間隔で流行のピークがみられていたが,2000年代に入って以降は,流行の増減に大きな変化がなくなっている。
梅毒は進行期により以下のように分類される。
早期梅毒:感染から1年未満の活動性梅毒。性的接触での感染力が強いとされる。
早期梅毒第1期:感染から通常1カ月前後(遅くとも3カ月以内)に,侵入門戸(口唇,口腔咽頭粘膜,陰部周辺,肛門周辺など)に丘疹,びらん,潰瘍などの一次病変がみられる活動性梅毒。所属リンパ節腫脹を伴うことが多い。初期硬結,硬性下疳は典型的な一次病変である。
早期梅毒第2期:感染からおおむね1~3カ月に,体内に散布された梅毒トレポネーマによる二次病変に基づく症状(梅毒性バラ疹,丘疹性梅毒疹,扁平コンジローマなど)がみられる活動性梅毒。一次病変が重畳することもある。
後期梅毒:感染から1年以上経過した活動性梅毒。性的接触での感染力はないとされる。症状は冒されている臓器によって様々であり,無症状のこともある。無症状でも活動性(要治療)と判断されるものは潜伏梅毒に分類する。
第3期梅毒:感染から年余を経て心血管症状,ゴム腫,進行麻痺,脊髄癆など,臓器病変が進行した状態にある活動性梅毒。感染後,数年~数十年後に心臓や脳などに障害が生じ,死亡することがある。
上記以外に,妊娠した女性が感染していた場合,胎盤を通して胎児も感染し重い障害をもたらす先天性梅毒も報告されている。
▶診断のポイント
梅毒遺伝子検査(PCRなど)は,検体採取に習熟していないと検出感度がよくないことが知られており,2024年時点で検査の保険適用はない。したがって,現実的には代理指標(surrogate marker)として,血清中の梅毒抗体を測定して診断する。梅毒抗体(RPR,梅毒トレポネーマ抗体)にはそれぞれ従来の2倍系列稀釈法と自動化法があるが,変動を細かくとらえられ測定誤差の少ない自動化法により,RPRと梅毒トレポネーマ抗体を同時に測定することを強く推奨する。RPRは梅毒の活動性を示すことに異論はないが,自動化法の感度が上昇したこともあり,RPR陰性で梅毒トレポネーマ抗体のみ陽性の早期梅毒の報告も増えている。梅毒トレポネーマ抗体陰性の場合,基本的には梅毒を否定できるが,梅毒を疑う病変や症状を認める場合,血清学的潜伏期(ごく初期の早期梅毒)の可能性を考慮して,1カ月後に再検査を行う。


残り1,631文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する