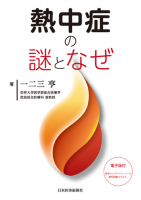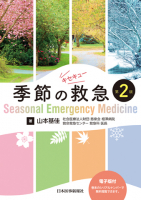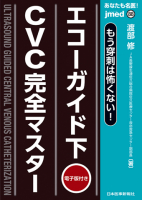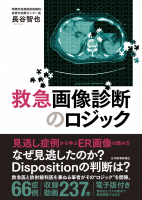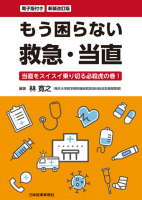お知らせ
胸部外傷[私の治療]
▶緊急時の処置
胸部外傷で特に緊急度の高いものは,閉塞性ショックをきたす,緊張性気胸と心タンポナーデである。
【緊張性気胸】
緊張性気胸は,肺外に空気が一方向に漏れ続ける病態であり,最終的には胸腔内圧の上昇から心臓の拡張障害をきたし,心停止に陥る病態である。身体所見では,頸静脈の怒張,気管の健側への偏位,呼吸音の消失,打診で鼓音の聴取などを認める。皮下気腫が認められることもある。循環動態に重篤な影響を与える気胸であり,画像検査の前に速やかな脱気処置が求められる。

一手目 緊急での脱気処置は,第2肋間鎖骨中線上を14ないし16G針で穿刺する。穿刺時に脱気音や,循環動態の改善がみられるかを確認する
二手目 その後引き続いて,胸腔ドレナージを考慮する。循環動態が安定すれば,X線検査やCT検査による精査を進めてもよい
【心タンポナーデ】
何らかの理由により心囊腔に血液が急速に貯留することで,心臓の拡張障害から,心停止を引き起こす病態である。身体所見では,頸静脈の怒張がみられ,エコー検査で心囊液の貯留を認める。循環動態が不安定な場合は,速やかな心囊液のドレナージが必要になる。
一手目 剣状突起左縁と左肋骨弓の交点やや下方から,エコーガイド下による心囊穿刺を行う。同部位から穿刺が困難な場合には,胸骨左縁第5肋間も選択肢となる1)。穿刺に引き続き,ドレナージチューブの留置を行う
二手目 凝血塊の貯留などで穿刺によるドレナージが困難な場合は,心囊開窓術を考慮する。心囊開窓術は通常,剣状突起下切開で行うが,経験を要する手技である
三手目 心停止に陥った場合は,左第4肋間で開胸し直視下に心囊切開を行う。心囊開窓術に難渋した場合もこの手技が考慮される
▶検査および鑑別診断のポイント
胸部外傷の検査として,胸部X線検査,エコー検査,胸部CT検査,心筋逸脱酵素を含めた血液検査,心電図検査が挙げられる。胸部X線検査やエコー検査は簡便に実施でき全例で考慮される。臓器損傷の精査には胸部CT検査が有効である。血管損傷が疑われる場合は造影CT検査を行う。心損傷が疑われる場合は,心筋逸脱酵素の測定や心電図検査を行う。また,心囊液の評価はエコーを繰り返し実施して行う。外傷性の気胸や血胸を認めた場合は,エコー検査や胸部X線検査を繰り返し行う。
▶落とし穴・禁忌事項
前述した緊急度の高い疾患の診断はあくまでも身体所見が重要である。画像検査の結果を待つために治療介入を躊躇することがないように注意する。また,胸部外傷は経時的に病状の悪化をきたすことがあるため,繰り返しエコー検査やX線検査で評価することが必要である。
▶その後の対応
X線検査,エコー検査,CT検査にて損傷部位を特定し,それに応じた治療を行う。通常,気胸はドレナージによる加療で治癒が期待できるが,気瘻が長期間持続する場合は肺切除や肺縫縮術などを考慮する。血胸もドレナージにより管理できることが多いが,出血が持続する場合(ドレナージ後2〜3時間にわたり200mL/時以上など1))は手術加療を考慮する。
胸部外傷の中で最も多い肋骨骨折は,多くの場合保存的加療となるが,胸腔内や大動脈近傍へ骨片が突出する場合や,フレイルセグメントを形成して呼吸機能の悪化がみられる場合は,肋骨切除術や固定術も適応となる。保存的加療の場合は,バストバンド固定や鎮痛薬投与を行う。また遅発性に血胸や気胸が進行することもあり,症状に応じ受傷後1週間程度で胸部X線検査も考慮する。
【文献】
1) 日本外傷学会, 監:外傷初期診療ガイドラインJATEC. 改訂第6版. へるす出版, 2021.
蛯原 健(大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター)
小倉裕司(大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター臨床検査科主任部長)