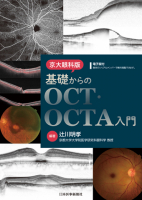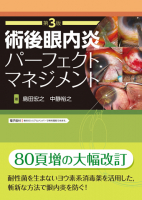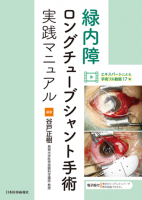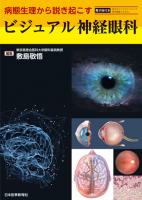お知らせ
ベーチェット病(眼病変)[私の治療]
ベーチェット病の眼病変では非感染性のぶどう膜炎がみられ,診断基準の主症状のひとつとなる。眼炎症の主な部位は前房,硝子体,網膜,視神経である。急激な眼炎症を生じ,視力低下や霧視,飛蚊症,結膜充血などをきたす。眼炎症は再発と寛解を繰り返す。
▶診断のポイント
新鮮例の急性期の眼炎症発作時では,非肉芽腫性ぶどう膜炎が両眼性にみられる。前眼部には角膜後面沈着物や前房炎症細胞,前房蓄膿がみられ,後眼部には硝子体混濁,網膜滲出斑,網膜出血を生じる。その際,口腔内アフタの合併が95%以上にみられ,眼炎症発作を繰り返し生じることがベーチェット病の眼病変の特徴である。

晩期例では,網脈絡膜萎縮,網膜血管の白線化,視神経乳頭の蒼白化などがみられ,重篤な視機能障害が後遺症として認められる。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
発作時の治療としては,前眼部発作のみの軽症例ではステロイドや散瞳薬(点眼薬)を使用し,後眼部発作を伴う重症例ではステロイドの眼周囲の注射(結膜下注射,後部テノン囊下注射)を行う。ステロイドの全身投与は,減量,もしくは投与中止時に激しい眼炎症発作が誘発され,結果として視力予後が悪いことが報告されており,わが国では一般的に用いられていない。
発作抑制治療としては,従来,第一選択としてコルヒチンの内服が用いられ,効果がみられない場合にはシクロスポリンの内服が用いられてきた。これらの効果不十分例に対しては,2007年からインフリキシマブが,2016年からアダリムマブが生物学的製剤として導入されている。

残り1,177文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する