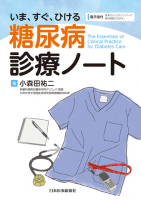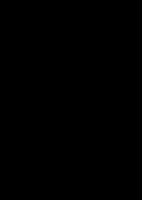お知らせ
糖尿病と心房細動の関連

【Q】
糖尿病と心房細動の関連について質問いたします。(1) ARIC(Atherosclerosis Risk in Communities)StudyやFramingham Heart Studyなどのコホート研究では,糖尿病患者は心房細動の頻度が高いことが示されています。その発症機序はどのようなものでしょうか。
(2) 糖尿病患者の心房細動治療におけるカテーテルアブレーションや抗凝固療法,心拍数調節治療の成績などについて。
以上,日本医科大学・清水 渉先生のご教示をお願いします。
【質問者】
桝田 出:武田病院健診センター所長
【A】

ARIC Studyでは1万3025名に対し追跡調査を行い,糖尿病は心房細動発症の独立した危険因子(ハザード比1.35,95%信頼区間1.14~1.60)であることが示されています。また,Framingham Heart Studyでは55~94歳の男性2090名,女性2641名に対して検討を行い,糖尿病の存在は心房細動新規発症の独立した危険因子(オッズ比男性1.4,女性1.6)であったと報告されています。これらの結果より,糖尿病が心房細動の危険因子であると考えられます。その機序について糖尿病心筋症の関与や自律神経障害,心房筋の線維化や酸化ストレス,炎症の関与などが指摘されていますが,いまだ明らかではありません。最近のメタ解析では,糖尿病があることで心房細動リスクは40%上昇し,相対危険度は1.24であったと報告されています。また,コントロール不良の糖尿病のほうがより心房細動を発症しやすいという報告や,糖尿病治療が心房細動新規発症を減らしたとの報告もあります。いずれにせよ,糖尿病はきちんとコントロールすることが必要です。
(2)カテーテルアブレーション等の成績
糖尿病患者と非糖尿病患者でカテーテルアブレーションの成績に差があるとの報告はありませんが,糖尿病患者の心房では伝導時間が延長しており,電位波高が低く,またカテーテルアブレーション後の再発が多いことが報告されています。その原因としては,糖尿病心筋症による心室拡張障害,また心房筋の線維化による心房リモデリングの関与が考えられています。
また,抗凝固療法に関しては,糖尿病の存在で既にCHADS2 スコア1点になり,他の合併症を有することが多く,多くの症例で抗凝固療法の適応となります。近年,糖尿病の存在は左房内血栓形成の重要な予測因子であることも報告されています。しかし,しっかりと抗凝固療法を行えば,糖尿病患者でも血栓症を予防することができます。
心拍数調節には主にβブロッカーが用いられますが,糖尿病患者と非糖尿病患者でその効果はほぼ同等と考えられます。一方で,糖尿病患者においては低血糖時の徴候である頻脈を修飾する可能性があり,使用には注意が必要です。