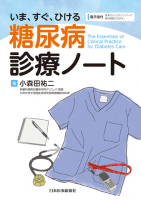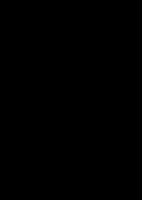お知らせ
SGLT2阻害薬によるケトン体の上昇の意味は?【心血管イベントのリスク減少機序としては,高ケトンよりも血圧低下,体液減少,交感神経の過緊張の解除が有力】

SGLT2阻害薬によるケトン体の上昇は,「飢餓性のケトン体産生」によるものと理解しています。最近,実臨床でこの製剤が2型糖尿病患者の心不全による入院や総死亡のリスク減少に関与するという報告が相次いでいます。障害された心筋において,ケトン体がATP産生に効率の良い基質になることや,脱水により増加するヘモグロビンが心筋により多くのO2を供給することなどが理由として考えられているようです。これらは,糖質制限食と水分制限を継続し,飢餓状態を保つことで,同じような効果が得られると思います。ケトン体の上昇が心保護作用の中核であるとすれば,あえてこの薬剤を投与する意味があるのでしょうか。
(愛知県 N)

【回答】
2型糖尿病では心血管疾患(cardiovascular disease:CVD)の早期罹患と死亡リスクを高めるため,新規糖尿病治療薬にはCVDリスクを改善させる効果に関する試験まで求められるようになっています。
タイトな血糖コントロールを行った臨床試験の結果では,細小血管障害の発症・進展を改善するものの,CVDに対する効果はなかなか明確には得られていませんでした。ところが,SGLT2阻害薬エンパグリフロジン(empagliflozin)を用いた臨床試験EMPA-REG1)では,CVDと全死因死亡率ならびに心不全による入院に対する驚くべき改善効果が発表されたのです。さらに,それに続いて実施された,同効果薬カナグリフロジン(canagliflozin)を用いたCANVAS試験2)でもほぼ同様の結果が発表され,CVDに対するこの効果は,SGLT2阻害薬のクラス・エフェクトであると考えられるようになりました。

残り703文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する