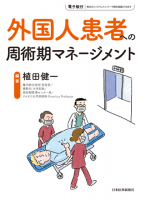jmedmook
お知らせ
麻酔への知的アプローチ<第12版>【電子版付】
| 著: | 稲田英一(順天堂大学名誉教授、地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院病院長) |
|---|---|
| 判型: | A5判 |
| 頁数: | 840頁 |
| 装丁: | 単色 |
| 発行日: | 2024年06月20日 |
| ISBN: | 978-4-7849-6214-3 |
| 版数: | 第12版 |
| 付録: | 無料の電子版が付属(巻末のシリアルコードを登録すると、本書の全ページを閲覧できます) |
| 診療科: | 麻酔・ペインクリニック | 麻酔・ペインクリニック |
|---|
目次
1:麻酔科学の発展性
2:麻酔は知的ゲーム
3:麻酔計画法
4:麻酔科医に必要な資質
5:麻酔科領域特有の疾患対処法
6:麻酔の安全対策
7:周術期における感染対策
8:術前診察と術前投与薬、術前経口摂取
9:麻酔導入
10:気道確保の基本的ストラテジー
11:気道のトラブル
12:筋弛緩薬とその拮抗
13:全身麻酔の維持と覚醒
14:気管挿管と陽圧呼吸の持つ本質的問題
15:循環モニタリング
16:輸液と電解質管理
17:輸血療法と凝固管理
18:脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔・神経ブロック
19:術後鎮痛と鎮静
20:体温管理と悪性高熱症
21:術後早期合併症と麻酔後回復室
22:脳神経外科手術の麻酔
23:心臓麻酔と循環管理
24:胸部外科手術の麻酔
25:産婦人科麻酔
26:小児麻酔
27:整形外科手術の麻酔
28:泌尿器科手術の麻酔
29:耳鼻咽喉科・眼科手術の麻酔
30:緊急手術の麻酔
序文
1990年に初版が出版されてから34年、ようやく第12版を上梓する運びとなった。ページ数は初版の3倍近くにもなった。初版は私自身の中のマグマのような熱量をもって書き上げた情熱の書であった。麻酔の安全性を高めるためにはどうしたらよいか、そのためには知恵をつける必要があるということを強調したかった。表紙の「知的」という文字が傾いている理由を知っている読者は少ないだろう。「これでよいのだろうか」という自戒の念を込めて首を傾げた様子を表現している。その後、様々な知見を加えることにより、本書は成長してきた。私自身の成長もさることながら、麻酔科学自体の成長や発展を示している。
34年間、ずっと付き合って下さった読者もいれば、その何年かを共有した読者、あるいはわずかな瞬間だけ遭遇した読者もいるだろう。私の思いの一部でも伝わればありがたいと思っている。
私にとって原点は、MGHの麻酔科レジデントとして自分の名前が彫られた胸壁聴診器を患者の胸に載せ、自分の耳に合わせて鋳型から作ったイアピースで、患者の心音や呼吸音を聴いた時のような気がする。胸壁聴診器の存在さえ知らぬ麻酔科医が多くなり、基本的モニタリングはパルスオキシメータやカプノメータと変わっていったが、パルスオキシメータが出す機械的な音や、カプノグラムの整った波形は、自分の中で心音や呼吸音としてとらえていた気がする。様々なモニタリングが開発されてきたが、モニタリングは患者と麻酔科医を結ぶ絆のような存在であると思う。麻酔管理に関する見方を大きく変えたのは、MGHでの集中治療フェローとしてのトレーニングであった。周術期全体を客観的に俯瞰することにより、周術期管理における麻酔管理の位置づけや重要性をより深く理解できるようになった。集中治療室を利用する各診療科の医師との相互理解も深まり交渉力が強化され、看護師、呼吸療法士などコメディカルとの連携も強くなり、快適な医療環境を築くことができるようになった。
薬物も大きく進歩してきた。治療域も広く、副作用も少なく、調節性の良い薬物が次々と開発されてきた。その投与方法もシミュレーションプログラムを取り込んだコンピュータ制御へと変わってきた。今後はさらにAIなどが麻酔科医の判断を大きく助ける時代になってくるであろう。
周術期管理も大きく変化してきた。術前外来が広く行われるようになって、術前評価や管理の質も向上した。前日夜からの絶飲食は、ERASに取って代わられた。超音波機器は、経食道エコー法や、肺エコー法などの診断に広く用いられるだけでなく、精度の高い超音波ガイド下の区域麻酔を可能にした。ビデオ喉頭鏡や、声門上器具など気道確保器具も進歩した。モニタリングの適切な使用や、困難気道ガイドラインなどの普及により、気道管理の安全性も増してきた。術後鎮痛も患者管理鎮痛法が広く用いられるようになり、患者は強い術後痛に苦しむことはなくなった。麻酔関連事故調査やClosed Claimsなどの調査から抽出されたリスクについては、ガイドラインが作成され、シミュレーショントレーニングが行われるようになった。
しかし、周術期管理が100%安全で、合併症も死亡も起こさないようになったわけではない。周術期心血管系合併症や急性腎障害などが起きたり、遷延性疼痛が続くこともある。幼若脳への悪影響や、高次脳機能障害が生じる場合もある。診断技術の進歩や、焦点を絞った評価により、以前は気づかなかった合併症も認められるようになってきた。以前は麻酔中の安全性確保が中心であったが、現在は術前評価から術後の予後に至るまで周術期全体を通しての安全性が問われるようになっている。麻酔科医はperioperative physicianとして、手術患者を守る必要がある。知識や技術、トレーニングの根幹となる周術期安全文化の醸成が、今も強く求められていると考えている。
本書に私が抱いていた情熱や思いが、新しい知識や考え方とともに伝わることを願っている。