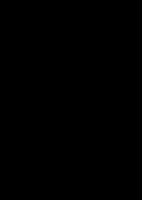お知らせ
■NEWS 【米国糖尿病学会(ADA)】SGLT2阻害薬による腎保護作用のメイン機序は本当に糸球体過剰濾過改善?:CREDENCE追加解析

昨年の国際腎臓病学会(ISN)で報告されたランダム化試験“CREDENCE”では、2型糖尿病例に対する、SGLT2阻害薬による慢性腎臓病(CKD)増悪抑制作用が示された。すなわち、2次評価項目ではあるが、SGLT2阻害薬群における「末期腎不全・血清クレアチニン倍増・腎死」の対プラセボハザード比は0.66の有意低値だった(95%信頼区間:0.53-0.81)。
SGLT2阻害薬によるこのような腎保護作用はこれまで、「糸球体過剰濾過の改善」を介すると説明されるのが一般的だった。そのため、SGLT2阻害薬開始直後、推算糸球体濾過率(eGFR)は一過的に低下するが、それは糸球体過剰濾過改善のマーカーであり、したがってその後、eGFRは改善するというものである。事実、多くの臨床データもこの仮説を支持している。

しかし今回のADAで報告されたCREDENCE試験の後付け解析は、このような理解に疑問を投げかけているようだ。12日のセッションでHiddo L. Heerspink氏(グローニンゲン大学、オランダ)が報告した。
CREDENCE試験の対象は、CKD合併の2型糖尿病4401例である。全例、忍容最大用量のレニン・アンジオテンシン系阻害薬は服用している。これらをSGLT2阻害薬カナグリフロジン100mg/日群とプラセボ群にランダム化の上、二重盲検法で観察した結果、SGLT2阻害薬群では「末期腎不全・血清クレアチニン倍増・腎/心血管系死亡」リスクが相対的に30%、有意に低下していた。
今回、Heerspink氏が報告したのは、試験開始後13週間のeGFR変化幅と、その後の腎転帰との関係である。「著明低下」(10%超)、「軽度低下」(0~10% )、「上昇」の3群で比較した。SGLT2阻害薬群では、プラセボ群に比べ、「著明低下」例が多く(45% vs. 21%)、「上昇」例は少なかった(27% vs. 49%、いずれも検定なし)。
目を引いたのは、これら3群のその後のeGFR低下幅である。SGLT2阻害薬服用例では、「著明低下」、「軽度低下」、「上昇」群のいずれにおいても、その後およそ40カ月にわたるeGFRの低下幅はいずれも約2.0mL/分/1.73m2で、群間に有意差を認めなかった。プラセボ服用例も同様で、当初のeGFRの変化幅にかかわらず、その後のeGFR低下幅はいずれの群も、およそ4.5mL/分/1.73m2で、群間差は認められなかった。
「腎関連重篤イベント」、「急性腎傷害」、「高カリウム血症」を比較しても、SGLT2阻害薬群、プラセボ群ともこれらリスクは、服用開始直後のeGFR変化に有意な影響を受けていなかった(諸因子補正後)。
なおHeerspink氏は本研究の限界の1つとして、同一個人内でeGFR測定値のばらつきが大きかった点を挙げ、「著明低下」、「軽度低下」、「上昇」分類が必ずしも正確ではなかった可能性を指摘していた。
本試験は、Janssen Research and Developmentから資金提供を受けて実施された。