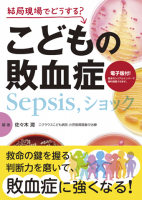お知らせ
尿路感染症[私の治療]
尿路感染症(urinary tract infection:UTI)は,腎から尿道に至る尿路で発生する感染症の総称で,細菌,ウイルス,真菌のすべてが原因となるが,狭義には細菌によるものを指す。小児においてはよくみられる疾患で,8歳までに女児の7~8%,男児の2%が罹患する1)。特に乳児期(1歳未満)の罹患率が高く,男児で約80%,女児でも約50%のUTIが乳児期に発症する。罹患率の性差に関しては解剖学的理由,すなわち女児は尿道が太く短く,膀胱まで直線的であるために細菌の侵入が容易である一方,男児は尿道が長く,また括約筋部の生理的狭窄が細菌の上行を困難にしているためと考えられている1)。ただし,新生児・乳児期(1歳未満)は男児に多い。
▶診断のポイント
UTIの診断においては,無菌的に採尿した検体を用いた尿培養検査で有意な細菌尿(中間尿の場合≧105CFU/mL,カテーテル尿の場合≧5×104CFU/mLの菌量の単一細菌の存在)を認めることが必須である2)。また,随時尿の沈渣における膿尿(鏡検で400倍視野当たりに5個以上の白血球を認める場合)の存在は,UTIを疑う重要な根拠となる。ただし,筆者の経験では,膿尿を認めないUTIが10~20%存在することに注意を要する3)。したがって,熱源不明の小児に対して抗菌薬の投与が必要と判断した場合には,投与前に検尿と尿培養を行い,UTIの鑑別を行うことが重要である。採尿においては,排尿が自立している小児では成人と同様,中間尿を採取できるが,排尿自立前の2~3歳未満の乳幼児では,カテーテルによる採尿が推奨される。なお,わが国のプライマリケアの現場でよく行われる,乳幼児の採尿バッグによる尿検体では,UTIの診断精度が低くなるため,推奨されない。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
UTIは上部UTI,下部UTI,および無症候性細菌尿の3つに大別される。すなわち急性腎盂腎炎,急性巣状細菌性腎炎,腎膿瘍など,腎実質で炎症が生じるものを上部UTIと呼び,臨床所見として発熱(39℃以上の高熱が多い)やCRPの高値を認める。一方,膀胱炎や尿道炎など,膀胱あるいは尿道に限局した感染症を下部UTIと呼ぶ。下部UTIは発熱を認めることは少なく,腎実質障害もきたさず,臨床的に頻尿や排尿時痛などの局所症状を伴うため,その診断は容易である。なお,無症候性細菌尿は検診で発見されることが多いが,診断や治療の必要性については様々な意見がある。
乳幼児の上部UTIにおいては菌血症や敗血症の合併も多いため,原則として入院の上で抗菌薬を経静脈投与する。治療期間は4~7日間の経静脈投与と,その後の経口投与を合わせ14日間とする。経口投与への変更は,全身状態の回復,尿所見の改善,CRPの陰性化を目安とするが,多くの場合,経静脈投与開始後1~2日のうちに解熱する。
小児におけるUTIの起因菌の80%以上は,グラム陰性桿菌(大腸菌やクレブシエラ属)であり,セフェム系抗菌薬が有効である。しかし10~20%はグラム陽性球菌(腸球菌属)が起因菌で,その場合ペニシリン系抗菌薬が有効である。したがって,可能であれば治療開始前に尿をグラム染色して検鏡を行い,グラム陽性球菌であればアンピシリンを投与する。セフェム系抗菌薬やペニシリン系抗菌薬が無効な場合,尿培養結果を参考に抗菌薬を変更するか,ESBL(extended-spectrum beta-lactamase)産生性の大腸菌を考慮して,メロペネムなどのカルバペネム系抗菌薬に変更する。
また,UTIを発症した小児の一部は,先天的な腎尿路の形態異常(先天性腎尿路異常)を有しているので,腎・膀胱の超音波検査を行い解剖学的な異常を検索する。超音波検査上の異常を認めた場合や,上部UTIを繰り返す症例では,排尿時膀胱尿道造影や腎シンチグラフィーなどを実施して,膀胱尿管逆流などをはじめとする先天性腎尿路異常の有無や腎瘢痕の有無を評価する必要性があるため,小児腎泌尿器専門医へコンサルトする。

残り744文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する