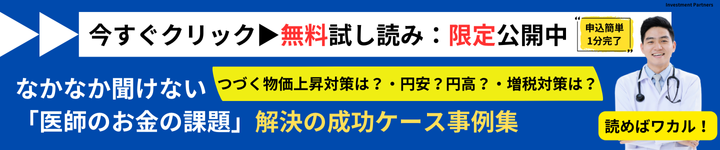お知らせ
医学的に原因が見当たらない痛みで受診した患者の治療方針について
No.5129 (2022年08月13日発行) P.53
渡邉恵介 (奈良県立医科大学附属病院ペインセンター病院教授)
柴田政彦 (奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学科教授)
登録日: 2022-08-16
- 診療科: 麻酔・ペインクリニック
- 麻酔・ペインクリニック
医学的に原因が見当たらない痛みで受診された方の治療方針について,奈良学園大学・柴田政彦先生にご解説をお願いします。
【質問者】
渡邉恵介 奈良県立医科大学附属病院ペインセンター 病院教授
【回答】
【痛みの原因を探るのではなく,痛みを主訴に受診したのはなぜかを考える】
痛みは本来動物にとって非常に重要で,身体の危険を知らせる警告信号の役割を持っています。人類が自然界の中で外敵や有害なものから身体を守り,生存確率を高め,種の保存に適した遺伝子を継承した結果,痛覚系という発生学的に古いシステムが今の人類にも備わっていると考えられています。しかし,このシステムは,現在のヒトの環境において必ずしも最良のものではありません。すなわち,身体が危険でも痛みを感じないこともあるし,身体が危険ではない状態なのに痛みが続くこともあります。医学的に原因が見当たらない場合は,身体が危険ではない状態なのに痛みが続いていると言ってよいでしょう。
「痛みの鑑別診断」や「痛みの緩和」に重点をおいた従来の診療は,医学的に原因が見当たらない患者にとっては益がないばかりか,痛みへのとらわれを強化したり,不幸感を高めることにつながりかねません。米国における医療用麻薬の氾濫やわが国におけるヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種後の副反応問題などの痛みに関連した社会問題は,医療界をはじめとする社会全体が,原因の明確でない痛みへの対応を誤った結果とも考えられます。「痛みには何か原因があるはずである」「痛みを緩和することは医療者の使命である」といった行きすぎた使命感が皮肉な結果をもたらしたと言えるでしょう。
残り595文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する