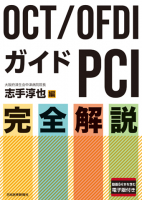お知らせ
■NEWS 【欧州心臓病学会(ESC)】SGLT2阻害薬によるHFmrEF/pEFの転帰改善を再確認:RCT"DELIVER"
左室収縮能の著明低下を認めない心不全(HFmrEF/pEF)は、転帰を改善する治療が長らく見つからなかったが、昨年の本学会でランダム化比較試験(RCT)"EMPEROR-Preserved"が報告され、SGLT2阻害薬による「心血管系(CV)死亡・心不全(初回)入院」抑制作用が明らかになった[医事新報. 2021;5089:64.]。加えて同様のデザインを持つRCT"DELIVER"も、26日からバルセロナ(スペイン)で開催された欧州心臓病学会(ESC)で報告され、HFmrEF/pEFに対するSGLT2阻害薬の有用性が再確認された。27日のScott D Solomon氏(ハーバード大学、米国)による報告を紹介する。
DELIVER試験の対象は、40歳以上で左室駆出率(EF)「>40%」、かつ、「左房拡大/左室肥大」と「NT-proBNP上昇」を認め、利尿薬使用下で症候性だった慢性心不全6263例である(含:入院例)。日本を含む世界20カ国から登録された。 平均年齢は72歳で、女性が44%を占めた。EF平均値は54%、NYHA分類「Ⅱ度」心不全が75%を占めた。 試験導入前の心不全治療は、77%でループ利尿薬、42%でアルドステロン拮抗薬が用いられていた。またレニン・アンジオテンシン系阻害薬も78%(5%前後のARNiを含む)、β遮断薬は83%で用いられていた。

これら6263例は上記治療を継続の上、SGLT2阻害薬(ダパグリフロジン10mg/日)群とプラセボ群にランダム化され、二重盲検下で2.3年(中央値)観察された。
その結果、1次評価項目の「心不全増悪(心不全による緊急入院・救急外来受診)・CV死亡」発生率は、SGLT2阻害薬群で7.8/100例・年となり、プラセボ群(9.6/100例・年)に比べ、有意なリスク低下を認めた(ハザード比[HR]:0.82、95%信頼区間[CI]:0.73-0.92)。試験期間を通した治療必要数(NNT)は32だという。 両群の発生率曲線乖離は、試験開始直後から始まった。一方、約1年経過以降は、両群間の差は拡がらなかった。
上記評価項目の内訳を見ると、有意低下が認められたのは「心不全増悪」(HR:0.79、95%CI:0.69-0.91)のみだった(「CV死亡」HR:0.88、0.74-1.05)。
また2次評価項目であるKCCQ-TS(QOL指標)も、SGLT2阻害薬群で、プラセボ群に比べ、8カ月間で2.4ポイント、有意に増加していた。なお、HFpEF例におけるKCCQ-TS改善は「7ポイント以上」で初めて、患者の重症度に対する全体評価(PGIS)が改善するとの報告もある[Butler J, et al. 2022.]。
安全性については、治療中止・一時中断を要する有害事象のいずれも、発現率に群間差はなかった。
目を引いたのは、試験開始時「EF」高低別の解析である。「40-49%」、「50-59%」、「≧60%」の3群間で、SGLT2阻害薬による「心不全増悪・CV死亡」抑制作用に差がないだけでなく、試験開始時EFが高値になるほど抑制作用は大きくなる傾向が認められた。 この点を、指定討論者のTheresa A McDonagh氏(キングスカレッジ病院、英国)は、先述のEMPEROR-Preserved試験(EF高値に伴い「CV死亡・心不全入院」抑制作用に減弱傾向)との違いだと評した(原因についての考察はなし)。
本試験はAstraZenecaからの資金提供を受けて実施された。 また報告と同時に、N Engl J Med誌ウェブサイトで公開された[Solomon SD, et al. 2022.]。