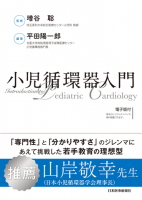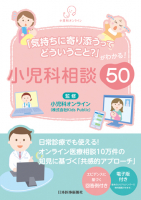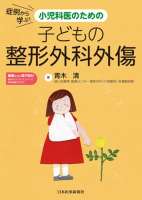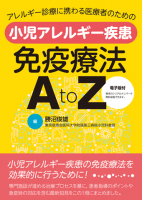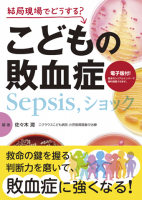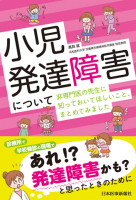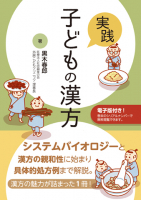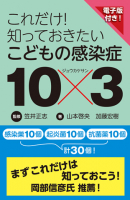お知らせ
急性脳症・脳炎(小児)[私の治療]
急性脳症は,発熱と痙攣・意識障害を主徴とする乳幼児の疾患である。2~5%が死亡し,30~50%に永続的な神経後遺症が残る。急性脳炎は,原因となる微生物の直接侵襲(もしくは傍感染性の自己免疫)により,脳に炎症が起こる疾患である。微生物の種類と宿主側の要因により予後は様々である。
▶診断のポイント
有熱時痙攣後に意識障害が遷延する場合に急性脳症・脳炎を想定する。意識障害をこまめに評価することが重要である。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
急性脳症・脳炎を診断した時点で,既に脳損傷は発生している。診療にあたっては,半日〜2日程度で不可逆的な脳損傷が完成しうると認識し,診断直後から必要な介入を迅速に導入することが重要である。診断前の疑診の時点で介入を開始する場合もある。
治療は,急性期治療(発症から2週間以内)と亜急性期治療(発症から6カ月以内)にわけて考える。
急性期治療は脳損傷をできるだけ軽くすることが目標となる。このためには,二次性脳損傷(呼吸不全・ショック・脳浮腫・痙攣重積・電解質異常・低血糖・高体温などによる予防可能な脳損傷)を最小限にすること,および急性脳症・脳炎の病態に合わせた特異的治療を行うことの2点を意識する。
二次性脳損傷を防ぐための方略は,成人領域で脳血管障害や心停止後症候群の管理で用いられている神経集中治療に準じる。急性症候性痙攣の管理にはしばしば難渋する。5種類以上の抗てんかん薬を併用することも稀ではない。初めは迷わず抗てんかん薬の種類と量を増量していくが,ひとたび痙攣が管理できたら抗てんかん薬を速やかに漸減していくことも重要である。
急性脳症については明確なエビデンスが確立している特異的治療法はない。急性脳症では「代謝異常」「興奮毒性」「サイトカイン・ストーム」の3者が病態形成に重要であることから,それぞれに対して,「ミトコンドリアレスキュー」「脳低温/平温療法」「ステロイドパルス療法」「ガンマグロブリン大量療法」を行う。急性脳炎では,原因微生物に対して最も治療実績のある抗微生物薬で治療する。
亜急性期治療は,後遺症に対するリハビリテーションが治療の主体となる。乳幼児は脳の可塑性が高いことから,発症から6カ月以内の集中的な包括的リハビリテーションにより,相当の機能回復を期待することができる。リハビリテーションと並行して,呼吸状態と栄養状態を整えること,および症候性てんかんを適切に治療することも,患者の長期的な発達予後のために重要である

残り1,784文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する